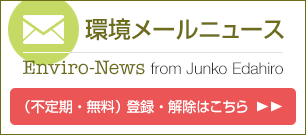エダヒロ・ライブラリーレスター・R・ブラウン
土壌の保護と再生
レスター・R・ブラウン
土壌浸食についての文献を見直していると、「土壌を保護する植生の損失」についての記述が何度も出てくる。過去半世紀の間、樹木の皆伐や過放牧、過耕作により、土壌を保護する植生はあまりにも多く失われてきた。そのため、長い地質時代にわたって堆積された土壌が速いスピードで失われている。
皆伐、過放牧、過耕作のような行き過ぎた行為と、その結果生じる生物生産力の低下をなくせるかどうかは、地球を覆う植生を再生しようとする世界的な取り組みにかかっている。そのような取り組みは、現在すでにいくつかの国で進行中だ。
1930年代に発生したダストボール(砂嵐)は、米国大平原を広大な砂漠に変えてしまう恐れのあるものだった。しかし、その衝撃的な体験から米国の農業慣習は画期的な変化を遂げた。風の勢いを弱め、それによって風食を減らすために畑の周囲に樹木を並べて植える「防風林」や、栽培地と休耕地を帯状に並べ、毎年どちらかの列に交互に小麦を植える「帯状栽培」が行われるようになったのである。帯状栽培を行えば、休耕地に土壌中の水分が蓄えられる上、帯状の栽培地が風速を弱め、休耕地の浸食も軽減できる。
1985年、米議会は、環境団体からの強い支援を受け、土壌浸食と主要作物の過剰生産を抑制するためのプログラム「土壌保全留保計画(CRP:ConservationReserve Program)」を策定した。これを受けて、非常に浸食されやすい土地に対して、農家が10年契約を結び、1990年までには約1,400万ヘクタールの土地が多年生の保護植物で覆われた。この計画のもと、農家は補助金を受けて、浸食の影響を受けやすい脆弱な耕作地に植物を植え、草地や林地へと転換したのである。
土壌保全留保計画のもと、1,400万ヘクタールの土地に草木が植えられたことと、全耕作地の37%にあたる土地で土壌保全対策が実施されたことにより、米国では、浸食による土壌の流出量が、1982年から1997年の15年間で31億トンから19億トンにまで減少した。非常に浸食されやすい耕作地を草地や林地に戻し、土壌保全対策を実施する、という2つの取り組みで土壌浸食を抑えようとした米国の姿勢は、他国に対して1つのモデルを提案しているといえよう。
農場以外の目的に耕作地を転換することは、農家の手に負えないことが多い。しかし、ひどい浸食による土壌の損失とダメージを受けた土地となると話は別だ。自然のプロセスによって形成された新たな土壌の増加量よりも、風食と水食によって引き起こされる土壌の損失量を少なくしようとすれば、世界的に莫大な労力を費やすことになるだろう。
かなり浸食されやすい耕作地の生物生産力を保護できるかどうかは、その土地が荒地になる前に草木を植えるかどうかにかかっているのだ。土地が本来持つ肥沃度の低下を食い止めるための第1ステップは、この急速に低下している生物生産力を、限界から引き戻してやることだ。
棚田は、水食の対処法として実績のある方法で、アジアの山岳地帯ではあちこちの水田でよく行われている。しかし、傾斜がそれほど急ではない場所では、米国中西部に見られるように、等高線帯状栽培がうまく機能している。
土壌保全対策の中からもう1つご紹介しよう。「保護耕作」という比較的新しい方法である。これには、土地を掘り起こしたり反転させたりしない――つまり耕起を行わない――「不耕起栽培」と、耕耘(こううん)回数を少なくする「最小耕耘法」の2つがある。
保護耕作を行うと、土壌の浸食が減るだけでなく、水分が貯えられ、炭素の含有量が増加し、作物栽培に必要なエネルギーを減らすことができる。やり方は、作物残滓で覆われた未撹乱土壌に直接種を筋蒔きするだけである。雑草は除草剤で駆除する。土地を鋤(すき)で耕してから円盤状の鍬(くわ)で掘り起こしたり馬鍬(まぐわ)でならしたりして苗床を用意し、さらに耕耘機で雑草を駆除する、といったやり方はしない。土に手を加えるのは、表面の種を蒔くところに細い切れ目を入れるときだけ。その他の部分は手を加えず、作物残滓に覆われたままにしておくので、水食と風食のどちらにも強い土地となる。
1990年代の米国では、農産物価格支持を受けるには、浸食を受けやすい耕作地に対して土壌保全計画を実施することが条件だった。そのため、1990年には700万ヘクタールだった不耕起栽培の面積が2004年には、2,500万ヘクタールとなった。
不耕起栽培は、現在、米国でトウモロコシや大豆の栽培に広く導入され、さらに、西半球でも急速に広まっている。2004年には、ブラジルで2,400万ヘクタール、アルゼンチンで1,800万ヘクタール、カナダ1,300万ヘクタール、オーストラリアでは900万ヘクタールの土地で行われており、米国を始めとするこれらの国々は不耕起栽培の先進5カ国となっている。
農家の人々が、いったん不耕起栽培の技術を習得すれば、この方法は瞬く間に広がる可能性がある。特に、政府が経済的優遇措置をとったり、作物助成金を得る条件として農業従事者に土壌保全計画の実施を義務付けたりすると、その可能性はさらに高まる。国連食糧農業機関(FAO)による最近の報告では、ヨーロッパ、アフリカ、アジアで、この数年の間に不耕起栽培が広がり始めていると伝えられている。
2000年12月、アルジェリアは、サハラ砂漠の北への拡大を食い止める手段として、国の南部に果樹園とブドウ園を集中させていることを公表した。これは、多年生植物が農地の砂漠化を阻止することを狙ったものである。2005年7月、モロッコ政府は、深刻な干ばつの対策に7億7,800万ドルを割り当て、農家の借金を帳消しにして、穀物を栽培していた土地を干ばつに強いオリーブ園やその他の果樹園に転換すると発表した。
また、サハラ砂漠の南端でも砂漠の南への拡大が懸念されている。ナイジェリアのオルシェグン・オバサンジョ大統領は、砂漠化対策の一環として、アフリカ大陸を5キロの幅で7,000キロにわたって横断する「緑の長城計画(Great GreenWall)」を提案した。
提案された植林地帯の西端に位置し、毎年5万ヘクタールの農地が消失しているセネガルは、この案を強く支持している。このプロジェクトに何年かかるのかは分からないが、セネガルの環境大臣であるモドゥー・ファダ・ディアーニュは次のように述べている。「貧困と砂漠化は、悪循環を生み出します……。私たちは、砂漠が襲ってくるのを待たずに、こちらから攻めていかなければなりません」
中国も独自の「緑の長城計画」によって、砂漠化の進行を食い止めようと努力している。それに加えて、砂漠化の進む省の農家には、耕作地に植林するための補助金も出している。目的は、1,000ヘクタールの穀物栽培地に植林することであり、その広さは現在の中国における穀物栽培地の少なくとも10分の1にあたる。
内モンゴル自治区では、砂漠化の進行を食い止め、生産的利用が可能な状態にまで土地を回復させる取り組みとして、砂丘を安定化させるために砂漠に低木を植樹している。また多くの場合、羊や山羊の放牧は全面的に禁止されている。
内モンゴル自治区の首府、フフホトの南に位置する和林県では、現在、第一次土地再生計画として、荒廃した7,000ヘクタールの耕作地に砂漠でも育つ低木を植樹することで、土壌を安定させた。この計画が成功したおかげで、こうした土地再生への取り組みはさらに拡大しつつある。
和林県で実施されている計画の中心となっているのは、これまで大量に飼育されてきた羊と山羊に代えて乳牛を飼育することであり、結果として2002年には3万頭であった牛の飼育頭数が、2007年には15万頭にまで増加した。牛は囲われた場所で飼育され、飼料として、トウモロコシの茎、麦かん、そして生産可能な状態に回復した土地で栽培されているアルファルファに似た干ばつに強い飼料作物が与えられている。県当局は、この計画によって今後10年間で和林県の収入は2倍になるだろうと予測している。
国内の放牧地の負担を軽減するために、中国政府は牧畜業者たちに現在飼育している羊や山羊の数を4割減らすように要請している。しかしながら、家畜の飼育頭数で豊かさが測られ、ほとんどの世帯が貧困にあえぐ地域社会において、家畜数を減らすことは簡単ではない。実際には、和林県の提案に沿って、代わりの生計手段が牧畜業者たちに提示されない限りは、おそらく難しいだろう。
放牧地として分類されている全世界の土地の4割で過放牧が行われている。こうした過放牧を廃止する現実的な方法としては、家畜の規模を小さくするしかない。過剰な数の家畜、特に羊や山羊は、植生を退行させるだけではない。その蹄は、土壌を保護する固い層――降雨によって形成され、風食を抑制する働きがある層――を粉々に砕くのである。唯一実行可能な選択肢が、家畜の囲い込み飼養だという場合もある。この手法をうまく取り入れ、酪農業を発展させたインドは、他国のモデルケースとなっている。
地球上に残っている植生を保護することは、当然、森林の皆伐を禁止し、択伐を推し進めることにもつながる。理由は単純明快である。一度皆伐すると、森林が再生するまでにかなりの量の土壌が失われるからだ。従って、その後2度、3度と伐採が繰り返されるたびに、土地の生産性はますます低下する。
地球上の草木の植生を回復することができれば、土壌浸食を防ぎ、洪水を減らし、炭素の排出を抑制することができる。それが、われわれの子どもや孫たちが地球上で生存し続けられるように、地球を修復できる唯一の方法なのである。