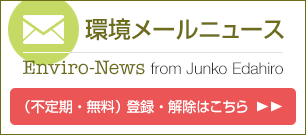エダヒロ・ライブラリーレスター・R・ブラウン
農業の地元密着化
レスター・R・ブラウン
最近米国では、地元でとれる新鮮な食材を食べることへの関心が急速に高まっている。遠くの産地から運ばれてきた食材の消費が気候に及ぼす影響や、ジャンクフード中心の食生活に起因する、肥満などの健康問題への懸念が増しているためだ。このことは、都会や学校での菜園作りや農産物直売市場の数が増えていることからもうかがえる。
急速に進む「食の地元密着化」傾向に伴い、食生活も、地元の食材や旬を以前よりも取り入れたものになってきている。今日、先進国の普通のスーパーマーケットでは、今がどの季節なのかが分からないことが多い。あらゆるものを一年中取りそろえようとしているからだ。
しかし、石油価格が上昇すればそれも一般的ではなくなるだろう。基本的に、食品の長距離輸送に使われる石油の量が減ることもまた――それが飛行機であろうと、トラックであろうと、船であろうと――地元中心に回る食糧経済へとつながるのである。
地元密着化へと向かうこのような流れは、近年米国で農場の数が増加していることにも反映されているが、これは、同国でここ百年来続いてきた農地集団化の流れに逆行するものかもしれない。2002年と2007年の農業センサスを比較すると、米国の農場数は4%増加し約220万となっている。
この間に新規参入した農場のほとんどは規模が小さく、その多くが女性によって運営されている。農業に従事する女性の数は、2002年には23万8,000人だったが、2007年には約30%増の30万6,000人へと急増した。
新規参入農場の多くは地元市場に出荷している。農場で生産される新鮮な野菜や果物の販売を、農産物直売市場や道路沿いに設置した自前の直売所に限定する農家もあれば、ヤギを飼育してミルク、チーズ、食肉を生産したり、花や、暖炉に使う薪材にする木を栽培する農場など、特定の農産物に特化しているところもある。また、有機食材を専門としている農場もある。2002年時点で米国には1万2,000の有機農場があったが、2007年にはその数は1万8,200となり、5年間で5割増という急成長を遂げている。
2009年春、ミシェル・オバマ米国大統領夫人が地元の児童たちとホワイトハウスそばの芝生の一画を掘り起こして家庭菜園を始めたことが、菜園作りの普及を大きく後押しするものとなった。
これには前例がある。第二次世界大戦中、当時の大統領夫人エレノア・ルーズベルトがホワイトハウスにビクトリーガーデン(訳注:戦時中の食糧不足を補うための家庭菜園)を作った。彼女が率先したことが刺激となり、やがて同国の生鮮農産物の4割を生産するまでになるビクトリーガーデンが何百万も作られたのである。
米国の大部分が農村社会だった第二次世界大戦中の方が、家庭菜園は今よりはるかに普及しやすい状況だった。しかし、現在、国内の住宅を囲む芝生の合計面積がおよそ7万3,000平方キロメートルにも上ることを考えると、家庭菜園が増加する余地はまだ非常に大きい。この中のほんのわずかでも新鮮な野菜や果樹の栽培に使えば、栄養摂取面の改善にも大いに役立てることができるだろう。
米国や英国の多くの都市や小さな町は、地域共同菜園を造成し、自分では菜園用地を確保できない人々が使えるようにしている。自治体の多くは、地域共同菜園用の土地を提供することは、子供のための遊び場や、テニスコートなどのスポーツ施設を提供するのと同じように必要不可欠なサービスだと考えている。
地元で作られた農産物には、多くの販路が開かれつつある。中でもおそらく最も知られているのは、地元の農家が自分たちの農産物を持ち込む農産物直売市場だろう。
米国では、このような市場の数が1994年の1,755から2009年半ばには4,700以上に増え、15年間でおよそ3倍となっている。農産物直売市場で生産者と消費者は、スーパーマーケットという人間味のない領域では存在しない人間的なつながりを取り戻している。
今では、多くの農産物直売市場がフードスタンプ(訳注:生活扶助のために政府が発行する食料割引券)も受け入れており、所得の低い消費者は、フードスタンプなしでは買えないような生鮮食品を買えるようになっている。現在、非常に多くの動きによって農産物直売市場への関心が高まっているため、将来その数はさらに急速に増えるかもしれない。
学校菜園では、子供たちが「どのようにして食べ物が作られるか」という都会の環境では欠如しがちな知識を身に付けている。そして恐らく、摘みたてのマメ、あるいは完熟したトマトを初めて味わうだろう。学校菜園はまた、給食用の新鮮な農作物の供給元でもある。この分野で先駆者であるカリフォルニア州には、6,000の学校菜園が存在する。
地元産の食品の方が新鮮で味もよく、栄養的にも優れており、学校の新たな環境意識啓発活動にぴったりだということで、今ではわざわざ地元産の食品を買っている学校や大学が多い。中には、厨房や食堂の生ゴミをたい肥化し、できた肥料を新鮮な農産物を提供する農家が利用できるようにしている大学もある。
スーパーマーケットは、地元で育てられた農産物が入手可能な季節に地元農家と契約するところが次第に増えている。高級レストランは、地元産の食材が料理に使われていることを強調している。食料品店の中には、果物や野菜だけでなく、肉や牛乳、チーズ、卵などの農産物を含め、地元産の食品だけを通年販売する店へと進化しているケースもある。
より遠くから輸送された食品は、風味や栄養分が失われる上、炭素排出量も押し上げる。アイオワ州で消費された食品の調査では、従来の農産物の輸送距離が平均約2,400キロメートルだったことが示された。これには、他国からの輸入品は含まれてない。
対照的に、地元農産物の輸送平均距離は約90キロメートルで、燃料の投入量にすると非常に大きな差がある。また、カナダのオンタリオ州で行われた研究では、輸入食品58品目の平均輸送距離が約4,500キロメートルだったことが明らかになった。
つまるところ、消費者は、長距離輸送型の食糧経済における食糧安全保障を懸念しているのだ。この傾向を受け、「ロカボア(地元産の食材だけを食べる人)」という新たな言葉が誕生した。これは、草食、肉食、雑食といったよく知られている言葉にもぴったり合うのである。
ほかにも、長距離輸送された食品の消費が気候に及ぼす影響を懸念する声に動かされ、英国の大手スーパーマーケットチェーン、テスコが、食料品が農場からスーパーの棚に届くまでに排出された温室効果ガスの量を示すカーボンフットプリントを商品に表示するようになった。最近ではスウェーデンが、栄養成分とともにカーボンフットプリントを食品に表示することでパイオニア的存在となっている。
農業が地元密着型になるにつれ、畜産物の生産も超巨大な牧場、養豚場、養鶏場から離れていく可能性が高くなるだろう。穀物・家畜混合方式に立ち返り、牛乳、食肉、卵の生産が工場式畜産から離れれば、地元の農家は家畜の糞を土に戻すため、栄養分の再循環が進む。
栄養分の再循環は、窒素系肥料を生産するのに使われる天然ガスの高値に、原料埋蔵量が枯渇状態のリン酸塩の高値が重なったことで、将来その重要性が一層高まることが示唆されている。この点では、地元市場向けに生産している小規模農家の方が大規模飼養業に比べ明らかに優位なのである。
畜産物を食べる量を減らすために食物連鎖を下へと進みながら、自分たちの食生活で生産地から消費地までの距離を短くしていけば、食糧経済におけるエネルギー使用量を激減させることも可能だ。そして、世界的な食糧不安が高まる中、自宅の裏庭や前庭、屋上、地域共同菜園などで自分が食べるものの一部を作ってみようと考える人たちもますます増え、農業の地元密着化をさらに進めることになるだろう。