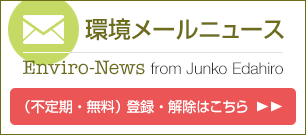エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
2005年05月17日
精神の脱物質化を進めよう
新しいあり方へ
何年もまえにベストセラーになった『清貧の思想』(中野孝次著)を、大変面白く読みました。
まえがきに
「いま地球の環境保護とかエコロジーとか、シンプル・ライフということがしきりにいわれだしているが、そんなことはわれわれの文化の伝統から言えば当たり前の、あまりに当然すぎて言うまでもない自明の理であった。(中略)
大量生産=大量消費社会の出現や、資源の浪費は、別の文明の原理がもたらした結果だ。その文明によって現在の地球破壊が起こったのなら、それに対する新しいあるべき文永社会の原理は、われわれの祖先の作り上げたこの文化−−清貧の思想−−の中から生まれるだろう、という思いさえ、わたしにはあった」。
というフレーズに、「清貧」(何という英語にするのでしょう!?)と「もったいない」、そしてフューチャー500会長の木内孝氏が力を入れていらっしゃる「倹約」にもつながるであろう"ポジティブな(前向きの)"メッセージを感じました。
本阿弥光悦を引いて、
「ひとたび所有欲にとりつかれると、人は所有の増大にのみ関心を奪われ、金銭の奴隷となって、それ以外の人間の大事に心が及ばない。家族への配慮とか愛とか慈悲とか、人間としての最も大事なことにさえ気が向かわず、富貴な人は必ず慳貪(けんどん)になる。そればかりでなく、物の取得や保全に心を奪われて、自らの精神の自由をさえ失っている」
だから光悦は、最上の茶器でさえも「やれ落とすな、やれ失くすな」と気を奪われるのがうるさいと、すべて人に与えてしまったくらいです、と書いています。
「所有を必要最小限にすることが精神の活動を自由にする。所有に心を奪われていては、人間的な心の動きが阻害される」という下りに、「清貧の思想とは、自我の狭小な壁に閉じこめられないための工夫であり、宇宙の生命に参じるための積極的な原理である」という著者の熱い思いもよくわかりました。
また「精神の脱物質化」ね、と思いました。
以前、パネルディスカッションでごいっしょさせていただいた太平洋セメントの谷口専務は「セメント会社は、山を削って石灰岩を持ってきてセメントを作って売るのではなく、他の産業や自治体から排出される廃棄物のマネジメントを商売とし、その副産物としてセメントができるからセメントも売る」という商売の脱物質化(=サービス化)をめざして、ゼロエミッション事業をどしどし拡大していらっしゃいます。
商売の脱物質化(=サービス化)は、世界の先進企業でも進んでいます。
「カーペットを売るのではなく、カーペットの提供するサービスを売るのだ」と販売からリースにビジネスモデルを転換し(ついでに巨額の原料コストを削減している)アメリカの世界最大の商用カーペット会社、インターフェイス社。
「これからますます厳しくなる環境の時代に生き残るためであって、別に地球のためにしているわけではありませんよ」と、洗濯機のリース(洗濯1000回分という洗濯機の提供するサービスを売る)の実験を始めているエレクトロラックス社。
これまで「イコール」で相関すると考えられていた「幸せ」と「物質的所有」を切り離す、ということです。「たくさん持てば持つほど、幸せか?」という問いにノーと答える人が増えてきているのは心強いです。
(その点でこの不況はひとつのチャンスだとも考えられます)
「幸せの脱物質化」「精神の脱物質化」も進めなくちゃ、ですよね。
『清貧の思想』には、私の生涯の研究テーマである<足るを知る><もったいない>も取り上げられています。
たとえば、『往生要集』(10世紀)には、「足ることを知らば貧といえども富と名づくべし、財ありとも欲多ければこれを貧と名づく」と書いてある、と紹介されています。
私は知らなかった言葉ですが、昔は関東の農村には「ものころし」という言葉があったそうです。たとえば、畑の作物を都合で完熟させないうちに廃棄せざるをえないとき、「あったらものごろしだなあ」というように使ったそうです。
「こういう言葉を作り出したのは、農民がその作るものを、コメでも野菜でも何でも、単なる市場価値においてではなく、生命あるひとつの命と感じていたからです」と著者は書いています。
将来の農業の図として、「ダイオキシンも環境ホルモンも心配ないよう、まったく土も使わず、工場製品のように生産される作物」というイメージ画を見たことがありますが、そのような世界では、作物は命とは見てもらえないのでしょうね。
『清貧の思想』でもうひとつ目を開かされたのは、「消費者」という、あまりにも馴染んでしまっている言葉についてでした。
「・・・そしてわれわれはただの人間ではなく、消費者という名で呼ばれるようになってきました。いつからこんな妙な言葉が使われ出したのか記憶は不確かですが、消費者というこの人間侮蔑的な言葉が1965年頃から、すなわち経済成長を一国の最大の目標としだしたころからの、われわれの状態を正しく言い当てているようです」。
「この生産の原理は、それが人間生活の幸福にとって必要だから作るというのではなく、作ることが技術的に可能だから生産し、生産したものが市場に迎えられれば成功であるということで、少なくともそこに人間の幸福への配慮はなかった」。
考えてみれば、「消費者」って本当にスゴイ呼び方ですね。企業がそういっているのはともかく、私たちも「消費者」という名と見方と役割に、あまり疑問も感じずにきているような気します。消費するっていうのは、私たちのひとつの側面に過ぎないはずなのですが。これからこの言葉にちょっと気をつけようっと。
もうひとつ、すごく面白かったのは、エーリッヒ・フロムが『生きるということ』の中でテニスンと芭蕉の詩を比較して、「持つこと」と「在ること」、西洋的感性と日本的感性を対比した様子を引用している箇所です。これはフロムの原書にあたってから、またご紹介しますね(大学の時に読んだ本を最近読み直すことが増えてきました。当時は何も感じなかったのに、今はとっても面白い)。
『清貧の思想』の最後の方に、こう書いてあります。
「本当ならば物が溢れている、何でも買うことができる、便利で快適になったというのは、生活を豊かに幸福にしてくれるはずではなかったでしょうか。なのに実状は、われわれはその中にいて幸福と感じることができず、むしろ人間性が物の過剰の中で窒息させられているように感じている。
どうしてこんな結果になったのか。物質的繁栄がわれわれに真の幸福をもたらさなかったとしたら、それはそのもう目的追求そのものの中にどこか間違ったところがあったと考えるしかないでしょう」。