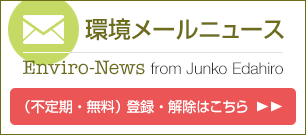エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
2006年02月09日
食料帝国主義に対抗して(2003.12.16)
世界のわくわくNews
食と生活
ワールドウォッチ研究所では、隔月刊で「ワールドウォッチ・マガジン」を出しています。今年の5/6月号に興味深い記事が載っていたので、実戦和訳チームに和訳をお願いしました。ご紹介します。
http://www.worldwatch.org/pubs/mag/2003/163/
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ワールド・ウォッチ・マガジン 2003年5/6月号
地元の食材を求める理由
バーモント州の小さな食堂で、革命が起こっている
ブライアン・ハルウェイル
バーモント州バール市の『ファーマーズ・ダイナー』食堂に立ち寄るといい。そこは、革命の真っただ中だ。しかし、それは一見しただけでは分からないかもしれない。それも無理はない。この町で有名なのは花崗岩を切り出したり、墓石を彫ったりするくらいだし、メインストリートに並ぶのはお決まりの市役所、映画館、金物屋、花屋、銀行、そして食堂だ。
この全部で60席の食堂には、緑色のビニールを貼ったスツール椅子が12脚、白いリノリウム材を使ったカウンターに並んでいる。バックカウンターには、1960年代に作られたガラス製のペストリー用ケースがあって、中に焼きたてのパイやマフィンが並んでいる。ステンレス製の牛乳入れがブンブン鳴りながら中身を冷やし、旧式のミキサーがいつでもミルクシェークを作れるように置いてある。厨房との間を仕切る開口窓の向こうでは、コックがオムレツとパンケーキをひっくり返し、ハッシュドポテトとベーコンの焦げたかけらを鉄板の溝によけている。この細長い建物に70年前に開店した当時の食堂の風景は、今もそれほど変わっていない。
ここには、早朝の常連客がいる。隠居生活に入った農民、州道の補修係が数人、電気工、配管工、その他さまざまな職人。彼らはこのどんよりした冬の朝、7時にはもう大きな白いコーヒーマグカップを手で包み込んでいる。1930年代スタイルの電灯が吊り下がり、ボックス席を照らす。
そこかしこで会話が響く中、わたしは食堂のオーナー兼支配人のトッド・マーフィーと話をしていた。コーヒーカップがソーサーに当たってカチャッという音がする。料理ができた合図のベルが、時折チンと鳴る。ウェートレスのスニーカーが木の床でキュッキュッと音をたてる。「息子が、うちのパパはフライドポテトのにおいがするって言うんだ」とマーフィーは話す。
でも、ちょっと長居すれば、ここは並みの食堂ではないということに気づくだろう。ミキサーと牛乳入れの中の牛乳は、有機の認証を受けている。つまり、この牛乳を搾った牛は、抗生物質を注射されておらず、化学肥料や殺虫剤を使った飼料も与えられていないということだ。また、これは地元の搾乳場から届いている。バール市民のほとんどがまだ行ったこともないような土地からタンク車で運ばれてきた牛乳とは違うのである。
オムレツに使う卵も地元産だ。マフィンやパイの材料のベリー類や小麦粉も、地元のベリー畑や小麦畑から届いた。フレンチフライは食堂でじゃがいもを切って作り、ハンバーガー用の肉もここで挽肉にする。牛肉も地元の農家が育てたものだ。実のところ、アメリカ人が口にする食べ物の大部分が、農場から食卓まで少なくとも2400キロほど移動しているが、この食堂で出される食べ物は、半径80キロ以内で育ったものがほとんどだ。マーフィーの目標はこれを100%にすることである。今は2月で、駐車場はまだ雪に覆われている。でも、ニューイングランド地方の寒い冬のさなかでも、メニューには、パンやパスタをつくる穀物から豆、肉、人参、じゃがいも、玉ねぎ、アップルソース、リンゴジュース、ビールまで、地元で作られたものが並ぶ。
メニューのカバーに、食材を提供する農家の人達の写真が使われているのに気づいた。(レストランで食べる料理が、特定の人から提供された食材を使っているだなんて誰が考えるだろうか。)
ビニール製のランチョンマットは、現代の食品流通制度のあり方に対して過激な意見を持った人達のいわば人名録といった感じだ。コロンビア大学の栄養学者であり郊外で農業を営むジョアン・グッソーの言葉を読んで、私はクスクス笑ってしまった。「私はマーガリンよりバターを好む。なぜなら、私は科学者より牛を信用するからである」。
また、ウェンデル・ベリーの有名な宣言文もあった。「食べることは、農的行為である」。そして、マーフィー自身の発言も引用されていた。「シンク・ローカリー、アクト・ネイバーリー(地域レベルで考え、ご近所で行動する)」。マーフィーは、地球規模で行動したり考えたりしている人を非難するつもりはないが、地球規模というのは自分には複雑すぎるようだ、と私に語った。「ご近所で行動するのなら、自分たちにも分かることだ」。
食堂は繁盛している。ウェートレスのメガンが話す。「この店の開店は毎朝5時半で、閉店は毎晩9時よ。お昼の時間帯はいつも忙しくて、週末もいつも混むわ。それに、季節が変わるときは毎日とにかく忙しくなるの」。オーナーは、さらに4カ所に店を開く計画を立てている。地場の食材がもっと食料品店の棚やレストランのメニュー、台所に並んで欲しいと感じている消費者や地元の農家、コック、環境活動家の関心が高まる波に乗っているのである。
しかし、このように多くの関心が集まっているからといって、すんなりいくとは限らない。「毎日ドラゴンと戦っているよ」とマーフィーは言う。これは、地元産の食材を基本にしたレストランを経営する際に立ちはだかる障害物を指している。例えば、大手の新規事業向けにつくられた煩わしい食品安全規制から、バー
モント州の農作物の多様性を奪うことにつながる近視眼的な農業政策、さらに、奮闘中の地元企業に圧倒的な力でのしかかるグローバルな食品銘柄まで、さまざまである。
本人が「大胆な実験」と呼ぶマーフィーのビジョンを聞いていると、まるで封建時代の話のようだと思わざるを得ない。マーフィーは、本気で革命について話しているのだ。ヨーロッパ全土で18世紀に貴族社会が崩壊した時のように、影響が甚大な権力交替になりそうなことを口にしている。クラフト社、モンサント社、
ADM社が、チューダー家、帝政ロシア皇帝、ルイ14世のように権力をふるっている現代の食品業界で、マーフィーは一生かけて、食の民主主義を勝ち取ろうとしているのだ。
「食の民主主義」という言葉は、一見、少し大げさで、しかも、奇妙な言葉の組み合わせのように思えるかもしれない。しかし、もし食の王国に勢力関係がないと思うのなら、フランセス・ラッペとアンナ・ラッペがその著書『希望の力』で主張した点を考えてみるとよい。
典型的なスーパーには、3万点もの商品が並んでいる。そのうちの半分ほどの商品が、食品・飲料の多国籍企業10社によって製造されている。そして、およそ140人の人間―そのうち117人が男性で、21人が女性―がそうした10社の取締役会を構成している。つまり、典型的なスーパーで目にする数限りない商品のおかげで、選択肢が豊富になったように見えるが、ほとんどの場合、真に農産物が多様だからではなく、包装や商品名が変わっただけのことである。それは、さまざまな地元産の多種多様な産物が、それを生産する何千人もの生産者から我々の元に届けられるのではなく、ほんの一握りの権力を握る経営幹部によって利益の最大化を目的に、世界中で規格化され選別されてきた商品なのである。
こうした帝国主義的な食品業界からの独立宣言が、我々の前に次々と現れ始めている。中には、例えばジョゼ・ボベ氏のケースのように、単に常軌を逸した行動としか思えないようなものもある。フランスの羊牧者であるボベ氏は、トラクターでマクドナルドの店に突っ込み、世界の食文化が均一化されることに抗議したのである。
メキシコのオアハカでは、同じような懸念を理由に立ち上がった市民団体が、由緒ある市の中心部に、マクドナルドの新店舗が建つのを阻止することに成功した。カナダでは、巨大な農薬・種子会社であるモンサント社の特許種子のいくつかが、パーシー・シュマイザーという農民の土地から発見されたあと、同社がシュマイザー氏に対して会社への批判を抑えるための戦略的訴訟を起こした際、同社に対する抗議行動が全国に広がった。(サスカチュワン州、サスカトゥーンにあるカナダ連邦裁判所は、シュマイザー氏がその種子を植えたという証拠を発見できなかったが、―その種子は、モンサント社の種子を使用している隣の農地から、シュマイザー氏の土地に風で飛ばされてきたものであることは明らかである―とにか
くモンサント社側に有利な判決になった。)そして、ヨーロッパでは、さらに多くの人々―政府を動かすに足る人数の人々―が、そうした遺伝子組み換え作物を米国から輸入することに抗議した。
何らかの意味で、こうした運動はすべて、地元の食糧供給と伝統的な食を守る活動である。こうした活動はすべて、単なる抗議行動ではない。爆発的に広がり、今や80カ国で7万5000人が参加するまでに成長したスローフード運動は、食の帝国主義に対抗する最大の組織化された運動である。
しかし、その運動の活力は、反対運動ではなく、その運動が守ろうとしているものから引き出される。つまり、人々をお互いに結びつけ、さらにその地域社会や土地と結びつけることで、良質の食べ物の社会的価値を守ろうとする動きがスローフード運動を支えているのである。スローフード運動のビジョンとは、一言でいうと「味わう権利」である。ファーマーズ・ダイナーのサービスはスローではないかもしれないが、食べるものを、ファースト・フードや大量生産された食品のマーケティング担当幹部の手に委ねないという点で、この食堂もスローフード運動と共通の立場をとっている。
「僕はこの土地に特別な思い入れがある。だから、バーモントの土地と生産者、そして食の歴史をみすみす危険にさらすようなことはしない」とマーフィーはきっぱりと言い切った。地元の食べ物を守ることに対する関心が急速に高まりつつあるのは、バーモント州だけではない。
植民地の惑星
食の独立宣言をした多くの人々は、「スローフード」という語にもかかわらず、この運動の緊急性が高まるのを感じている。食べ物はさらに遠くまで輸送され、以前より少ない数の多国籍企業によって牛耳られている。長期の貯蔵と遠方への(より少ないコストでの)輸送を可能にする技術の進歩によって食糧の供給範囲が広がり、さらに、安価なガソリンと輸送補助金によってそうした拡大が促進された。世界の食品貿易額は1960年以来3倍になり、貿易量は4倍に膨れ上がった。アメリカでは、一般的な食料品が輸送される距離は、2500キロから4000キロである。その距離は、1980年と比較して、約25%伸びた。イギリスでは、20年前と比較すると、食料品の輸送距離が1.5倍になった。
カナダ、リジャイナ大学の社会学者、ジョアン・ジャフ氏は次のように言った。「現在の食の市場において、投票権、もっと根本的にいうと、主導権という点で著しい不均衡がある。距離や加工処理により、人々がますます食物源から切り離されるにつれて、主導権が奪われた状況は、最近数十年間にわたって着実に進んでいる」。そして、恐らくこうした主導権の問題こそが、最近始まった、地元の食物を食べようという世界的な動きを推し進めているのであろう。
バンクーバーで食に関する活動を行っているハーブ・バーボレット氏は、地元が主導権を持つということは、単に、グローバル化する産業に対して州レベルで漠然とした抵抗を行うことではない、と指摘している。非営利の「農民仲間・都市住民仲間(FarmFolk/CityFolk)」という組織の創設者であり代表でもある同氏は、次々に具体的な利点を挙げた。
・「食物を輸送するための、化石燃料の使用や交通渋滞が減る」。(調査によると、輸入された食材から作られた基本的な食事に消費するエネルギーとそれに伴う温室効果ガスの排出量は、地元の食材から作られた食事のゆうに4倍に相当する可能性がある。)
・「地元の農地と生産者の保護」。(地元に市場を持つ生産者は、廃業率が低い。)
・「最高の風味」。(二重盲検試験によると、被験者は常に、長い距離を運ばれ、鮮度の低くなった食物ではなく、生産者が作って市場に出したものを選ぶことが分かった。―このようなことが一因となり、地元の食材を利用しようという動きが、世界中のコック、料理評論家、舌の肥えた消費者の注目を集めてきたのである。)
バーボレット氏のグループは、そうした目標を達成するために、食物輸送体制を整え、生産者の市場を促進したり、屋上庭園のプロジェクトの立ち上げを支援したり、良質な食物の選択が限られているバンクーバーの都心部で、ヘルシーなカフェを開店したり、地域の大きな公園を再び農地として活用するというようなさまざまな取り組みを行ってきた。
安全性が高い?
バーボレット氏は、地元の食べ物の利点を挙げていたが、一瞬沈黙し、それから、もうひとつ付け加えた。「食品の安全性に関するリスクが減る」。
この最後の利点はすぐに目に見えて現れるものではないかもしれない。しかし、何千キロもの距離を輸送され、多数の人の手を経てきた食べ物は、多くの汚染の機会にさらされている。例えば、2001年にイギリスで口蹄病が発生したが、その結果、イギリス産の肉の売上は急激に落ち込み、農村は大打撃を受けた。
口蹄病は、1967年に発生した時よりも、かなり広範囲に急速に広がった。それは、現在、家畜が国内各地から中央の屠殺場に運ばれているのが主な原因である。1967年当時は、屠殺や消費が、ほとんど地域レベルで行われていた。また、調査によって、最近発生した口蹄病の場合は、感染した家畜の飼料がはるか中国から輸入されていたことが分かった。口蹄病は、人間には感染しない。しかし、食物の輸送
距離が長いということは、病原菌(大腸菌、リステリア菌、炭疽菌など)がたちまち広範囲に広がり、多くの人がそうした菌にさらされる可能性があるということである。
最近のテロ事件の後、集約化の進んだ、遠隔地からの輸送に依存した食糧体制を、異物混入や交通遮断との関係で不安視する声が特にアメリカであがっている。(ある試算によると、アメリカ西部のほとんどの主要都市では、手元においてある食糧はせいぜい2日分止まりで、突然輸送に障害が発生すると大問題になるという)。食糧の遠隔地依存にはこうした問題以上に安心感にかかわる問題がある。
地元の食材を使った料理には、産地が分かっているという、独特の安心感があるためだ。例えば、トロピカーナの商標があるりんごジュースの瓶には、「ドイツ、オーストリア、ハンガリー、アルゼンチン、チリ、トルコ、ブラジル、中国、或いはアメリカの濃縮果汁」を使ったことが明記してあるが、農薬の使用基準は各国でかなり違いがある。したがって、口に入る食べ物がどこの生産地のものなのかわかっていれば、大変に幸運なことなのだ。
ところで、人々は地元での食糧生産のことに意見を言えるようになると、周囲の土地の利用状況、水中に流された汚染物質、近隣住民の暮らしの安全、といったことにも物申すようになる。マーフィーも「生産者のことがすべて分かっていると、お客はとても楽に、抗生物質を与えられていない牛肉や有機牛乳や遺伝子組替えのない穀物を、選ぶことができるからね」と話している。
「ある意味では、これは自国の安全保障に関わることですわ」、と話すのは、バーモント州において農家と料理人の間の橋渡しをしているバーモント・フレッシュ・ネットワークの支配人、ニーナ・トンプソンである。「もし社会の輸送基盤がテロによって壊されてしまったら、一体どんなことになるのでしょう。ここは、
大丈夫でしょうけどね」と。
地元の食糧と地元の経済
ファーマーズ・ダイナーで、マーフィーは自ら作成したマスタープランを説明してくれた。彼の口からは、熱に浮かされたようではなく、よく物事を考えるビジネスマンのように、淡々と言葉が飛び出す。マーフィーは細身の魅力的な人物で、年は30代、私が訪問するに当たって聞いていたのは、茶色がかった金髪のストレートヘアーをポニーテールにした男性ということだった。標準的な食堂では食材の仕入先数はせいぜい5つ位だが、大抵の所はもっと少ない、とマーフィーは説明する。
こうした仕入先は世界的な規模で農業を展開している、シスコ社のような巨大企業の経営支配下にあるという。シスコ社といえば、北米最大の食品流通会社であり、フォーブス誌の評価では、食品加工会社としても2番目にランクされる程の大企業である。大抵の食堂やレストランはシスコ社に電話注文をしさえすれば、18輪の大型トラックが食糧を配達してくれる、とマーフィーは話してくれた。
これとは対照的に、ファーマーズ・ダイナーでの食材の仕入れ先は、ざっと数えて35カ所程になる。来年はさらに仕入れ先を20カ所増やす計画があるのだと言う。ダイナーズ食堂は、開店当初の半年間で、食材購入予算の70%を、食堂から半径80キロ以内で栽培された食品の仕入れに充てていた。
彼は"pod"と呼ばれる計画で、この割合をさらに高めようとしている。食堂の隣には州政府の認可した食肉加工施設を設け、反対側にも同じく認可済みの食品加工施設を設置して、そこで、缶詰や食品の乾燥、パンを焼くのだという。「ほとんどの食堂は、予めスライスした冷凍の人参を使っているがね」とマーフィーは話した。「でも、うちは、地元の旬の人参を加工するし、ほかにもそれ以外の季節に備えて、冷凍したり、ピクルスにしたり、缶詰にもしたりできるよう、設備を整えておくことが目標なんだ」。
マーフィーは、この"pod"計画によって、地元の食材を使う割合を増やすにあたって大きな障害となる問題に対し、予め手を打っておこうとしている。地元の農作物を再び多様にすることや、度重なる合併の波に呑まれて疲弊してしまった食品加工能力を、元通り回復させることが困難となっているためである。
「多くの地域では搾乳農家が失くなり、チーズ生産業者が消え、缶詰業者が去っていった。パンを焼く店さえもなくなったよ」と、アメリカに本拠を置く、地域食品安全連合会の会長、アンデイ・フィッシャーは語る。この点、バーモント州は国内や海外の大半の地域に比べ、随分恵まれている。ここでは、国内では最も多様に農業が展開されており、全耕作面積のうち、州が有機栽培として認めた農地面積の割合は、どの州よりも高い。農場で作られるチーズの種類も50を超えバーモントに続く5つの州でのチーズの種類を合計したよりも多いのである。
「僕たちはこの食堂が触媒の働きをしてくれれば良い、と願っている。農家や食品業者がここで新しい商品や作物を作るきっかけを、見つけてくれるようにね」と、マーフィーは話している。食品を加工する店が食堂の隣にあれば、農家が捨ててしまうような、二等品や傷んだ果物や野菜だって、スープやジャムやチャツネを拵えるのに利用できる。マーフィーが地元農家との関係を発展させてゆけば、食堂の経費も実際下がってゆく。
「もし、毎月使用するじゃがいもや玉ねぎやトマトの分量が分かれば、農家だって収入の目途が立つからね」と彼は言う。農家は資金繰りや懐具合を心配しなくて済むから、結果的にはマーフィーに対しても、安い値段を提示できるわけである。
マーフィーの住むバーモント州の一角で食糧の自給率が高まると、必然的に人々の食品に支払うお金がますます地元に還元されるようになる。というのは、配送や保管、仲介手数料の支払いに流れる金額が少なくなるからである。この食堂では、今では毎月地元の農家から1万5000ドル分の作物を購入している。この金額は、食堂が拡張されてゆけば更に増える、とマーフィーは話している。「僕は農家宛ての小切手を書くのが好きでね」と彼は笑いながら言った。彼は最近、この食堂のために豚を飼育した場合、農家の経営が成り立つのかどうか検討中だという、農家の息子とも何度か話をしていた。
自給率を高めようとの議論が、ロンドンの新経済財団から発行された最近の研究報告書で裏付けられている。当報告書によると、地元の食品業者に支払われた10ポンドは、地元に25ポンドの価値を生み落とすが、同じ金額がスーパーマーケットで使われると、地元にもたらされるのは14ポンドでしかないという。通貨単位がポンド、ペソ、ルピーと何であれ、地元の経済にとっては、地元で消費したお金がほぼ2倍の所得となって還元されているわけである。
この乗数効果による数値を、ほとんどの農村経済地域で見受けられる、より植民地的な関係と比較してみよう。ミネアポリスにあるクロスロード資源センターのエコノミストであるケン・メーターとジョン・ロサールは、最近、ミネソタ州南東部における農家の1997年の農産物収入が8億6600万ドルで、これに対し、農作に使われた金額は、9億4700万ドルであったことを突き止めた。これは主に、遠隔地の仕入れ業者や、債権者、不在地主に対する肥料や農薬、地代の支払いである。(もし、連邦政府からの補助金がなければ、多くの農家は経営を維持することができないだろう)。
一方、この地域の住民は年間5億ドル以上の食糧を購入しているが、それは専ら地域外に地盤を持つ生産者や販売会社からである。国内最大の飢饉救済組織の会長を務めるダグ・オブライエンは、アメリカ中西部の住民の矛盾をついている。つまり、「この地域では、何千エーカーもの土地でコーンフレーク用のとうもろこしが栽培されているのに、住民は1箱のコーンフレークを子供に食べさせるために困窮者のためのフードバンクに通っている」と。全体では、現在の農業の関係でみると、毎年約800万ドルが地域の経済から搾り取っている、とメーターとロサールは結論付けている。
遺伝子組み換え作物を提供するアメリカ
ここ何回か話をしたときのマーフィーは、息をつく間もないほどだった。食堂の経営だけでなく、マスコミの電話取材に応対するのにも忙しい。ファーマーズ・ダイナーは、高級料理雑誌『グルメ』ですでに取り上げられ、ニューヨーク・タイムズ紙のグルメ欄と地方誌『バーモント・ライフ』でも近日中に記事になる。マーフィーは、自分の「とんでもない食堂さ!」という言葉が紹介された最近の記事を読んだかと聞いてきた。そしてすぐに、そんなことは言っていないのに、と言葉を継いだ。
このように料理界の一流マスコミが注目しているのだが、地元産の食べ物に対するこうした関心の高まりを、一時的な流行だと片づけてしまうのは簡単だろう。だが、大都市の中心部を見てみよう。酒屋やファースト・フード店は十分すぎるほどあるのに八百屋は1軒もなく、新鮮な果物や野菜を手に入れられるところといえばファーマーズ・マーケットぐらいだ。そして一方、食料を輸入する経済的余裕はないが、政府の適切な支援があれば国内の食料生産を増やせる貧しい国に目を向けたならば、食料の地元生産という恩恵を受けられるのが富裕な人々には限られないことが分かる。
最近、カリフォルニア州を本拠とする経済シンクタンクで「フード・ファースト」として知られる食糧開発政策研究所のアヌラダ・ミッタル所長とこの点について話し合う機会があった。このシンクタンクは、「緑の革命」、世界貿易機関(WTO)、遺伝子組み換え種子、生命特許に対する批判で有名だが、ミッタル所長
は地元産食料に特に関心を抱いており、そういった一連のよからぬ動きに対抗するための有力な方策になるものと考えている。
ミッタル所長は私に「食料の地元生産とは、国際市場の気まぐれと国際貿易協定の命令から自立することだ。食料の自給自足が崩れ始めると、たちまち飢饉へとつながる」と語った。そして食糧の備蓄がない貧しい国々は、「乞食に選り好みは禁物」だと気づくだろう。
ミッタル所長は最近起こった、外交筋にとっての悪夢といえる事例を挙げた。飢饉に直面していたザンビア政府が、遺伝子組み換え作物の含まれたアメリカからの食糧援助を拒否したのだ。アメリカの交渉担当者は、国民の命を危険にさらしているとしてザンビア政府を非難したが、その後、結局、遺伝子組み換えでない穀物を探して提供することと、さらに、提供した遺伝子組み換え穀物については、ザンビア農民がそれを作付けすることのないよう粉砕することに合意した。だが、この出来事によって食料主権についての問題点が浮かび上がった。
ミッタル所長はさらに、世界農業の指針はおよそ民主的とは呼びがたいものだと主張する。1999年にシアトルで開催されたWTO閣僚会議が決裂したのは、「交渉」と呼ばれるもののほとんどが、大半の国を締め出した密室の取引で進められている事実に抗議して、第三世界各国の通商大臣が退席したからだという。そして、WTOの「農業に関する協定」の文言は、多国籍の食品加工企業であり商社でもあるカーギルの副社長が草案をまとめたのだと語った。
「これは食料デモクラシー(民主主義)ではなく、食料ヒポクラシー(偽民主主義)だ」と言うミッタル所長の説明によると、ここ何回かの多角的貿易交渉で、欧米諸国は、貧しい国々にはまんまと関税を引き下げさせておいて、自国の関税と国内農業への補助金は高く据え置いたという。
インド出身のミッタル所長に、インドの作物多様性の維持と食糧の自給自足促進を支援するナブダニャ(「9つの種」の意)運動についてたずねた。1991年に組織されたナブダニャは、その土地在来の小麦やコメなどの穀物種を特許から守るために目録にまとめ、そうした穀物種が共有財産であることを宣言している。ナブダニャは地域運営による種子バンクや農業用品店、貯蔵設備を設け、化学肥料や農薬、遺伝子組み換え種子、生命特許の拒絶を誓った村々を「自由のための地帯」という組織として確立する支援をしている。
この場合の「自由」は経済的な自由と環境的な自由の両方を意味する。地域ごとの穀物が多様であれば、高価な農薬の投入などに依存しなくなるし、害虫の大発生や気候の変化に対する弾力性が生まれる。そして、農家が輸出市場ではなく地元市場向けに生産すれば、顧客層が著しく多様化し、幅広い農作物の作付けが促進される。このようにして、穀物の多様性が自給自足を後押しする。
ミッタル所長は次のように語る。「ナブダニャは地域レベルでおきている数多くの動きのひとつにすぎない。地域の人々はどれほど状況が切迫しているかを悟り、生物多様性の喪失や環境破壊、生計手段の破壊に立ち向かおうとしているのだ」。インドだけでも数百の運動があるが、タイの「遺伝子組み換え作物に対する抗議行進」(生物多様性と地域作物の多様性重視にむけての地元主導の運動)、ブラジルの「土地を持たない労働者運動」(大規模地主の土地に土地を持たない労働者や農家を入植させ、ブラジルの不均衡な土地分配を是正するための運動)などの例もあると彼女は指摘する。
もちろん、ミッタル所長も認めるだろうが、ある程度の食品貿易は自然で有益である。しかし、自給自足を拡大すれば、値動きの激しい国際市場から国民を守り、国内に富と雇用を生み出し、いつでも頼れるわけではない遠方の国や企業への依存を避けることができる。
食料革命の戦士たち
ファーマーズ・ダイナーは単独でバーモント州の農業を改革しようとしているのではない。この騎士物語は大勢の脇役たちに支えられている。バーモント州土地信託が行っているプログラムは米国でも数少ない成功をおさめている。就農後間もない農家に対して低金利融資や助言、減税措置などの援助を行い、有利なスタートを切れるようにしているのだ。バーモント州の人々はいまや、バーモント産の食材を買うときだけに使える地域通貨を、少なくとも3種類(バーリントン・ブレッド、グリーン・マウンテン・ドル、バッファロー・コープ・ドル)使っている。
また、バーリントンのインターベール基金は、350世帯に食材を供給する地域農場の設立を支援している。同基金は、農家のネットワークを作り、地域の病院に野菜、果物、ハーブをほぼすべて供給するほか、農家や食品事業者が食品加工やケータリング事業を試すことのできる、地域の実験調理場も計画している。
バーモント州内の数百のレストランが、すでに近隣の農家や食品企業から食材を調達するようになっているが、これは主に、バーモント州の農業活性化のために6年前から活動している非営利グループのバーモント・フレッシュ・ネットワーク(VFN)の努力によるものである。同ネットワークのニーナ・トンプソンは、
契約はすべて握手によって成立する、という。レストランがネットワークのメンバーであり続けるためには、少なくとも3回違う人と握手しなければならない。また、農家は少なくとも1回握手をしなければならない。
VFNは毎月、地元の農家から調達できるすべての食材をリストアップした「フレッシュ・シート」を作るので、これを見ればシェフは一度で仕入れを済ませることができ、農家はまとめて販売できるわけである。VFNは、多くの農家やレストランが重複して手間をかけていることに気づいた。「すぐ近くの3軒の農家
が、同じ町の違う買い手に、違う作物を3回ばらばらに配達しているケースさえあった」とトンプソンは語る。「今では彼らはひとつの車を使って1回の配達ですませ、お互いの顧客に宣伝して販売先を拡大することもできるのだ。」
このような支援の必要性は広まっているようである。イギリス南西部でも同じような試みが展開されている。デボン州フードリンクは1998年から地元生産者と地元の食品店を結びつける事業を実施している。この政府出資事業は、年間50万ポンド未満の予算で、推定150人の新規雇用を生み、15のファーマーズ・マーケットと18の宅配サービス(米国ではCSAとして知られる食品配達契約システム)を生み出している。また、多くの食品ビジネスを成功させ、推定900万ポンドの地域経済を支えている。
デボン州では、バーモント州と同じように政府または地元グループの役割の必要性がはっきりしている。フードリンク設立者のイアン・ハッチクロフトは次のように語る。「われわれは、地元市場の失敗を解決するために『介入』しているのだ。民間セクターは地元食品企業に大規模に投資しておらず、多くの場合、状況は地元食品企業に不利だからだ」。
トンプソンも同意見である。「ロビイストはほかのどの分野にもいるのに、地元農業には利益団体がいない」。地元食料生産の提唱者たちは大きなロビー団体ではないが、彼らを支持する人々は増えている。このような人々のグループには、家でガーデニングをする人や、近所に作物を売りたいと考える農家、学校の食堂ででる食物を気にかける親たちや、家庭料理を家族で楽しむ人たちの一人ひとりが、潜在的に含まれている。彼らは、ますます変形し、消毒され、産地の分からなくなった食材に対し、小規模ながら強力な反対運動を繰り広げているのだ。
ファーマーズ・ダイナーの創立者はもちろんのこと、この冬の日にファーマーズ・ダイナーにつめかけた50人あまりの人々も、このグループに入る。マーフィーはコネティカット州の酪農農家に生まれたが、残念なことに彼の家族は、彼が農業をできるようになる前に動物をすべて売り払わなければならなかった。「僕はこの33年間を、農業に戻るために費やしたのだ」と彼はいう。彼は妻と一緒に羊100匹の酪農業を始めており、いつの日か彼のチーズと子羊肉をファーマーズ・ダイナーのメニューにのせたいと考えている。
(ブライアン・ハルウェイルはワールドウォッチ研究所の上席研究員である)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ブライアンは物静かな若手研究者です。レスターが研究所にいた頃は、レスターのアシスタントとして農業・食を研究していましたが、いまでは研究所のこの分野の専門家になっているようです。
世界の食糧を牛耳っている多国籍企業やWTOのお膝元ともいえるアメリカで、このような動きがあちこちで広がっているのですね。「私たちは選ばされる必要はない。自分で選ぶことができる」という思いを再認識しました。夕飯の買い物へ行ったときに「何を買うか」をちょっと考えて、変えれば、「自分で考え、選
ぶ」ことを実践できます。
海外のMLで、面白いウェブページの紹介がありました。Factory Farm(効率や儲けだけを考えて、薬漬けで食肉を作っている工場化した農家)に関する警告と「ではどうしたらいいか」という行動および情報源をまとめたページです。(英語ですが、アニメもよくできていて、取り組みとしても興味深いです)
http://www.themeatrix.com/
また [No.871] の「小さな循環:身土不二、地域通貨、フードマイレージ」でも、同じテーマについて「循環」という視点でご紹介しています。ブライアンの記事にも考え方が出ていましたが、フードマイレージについても日本の数字がありますので、ご紹介します。日本の状況はアメリカ以上です(「以上」というか、
「以下」というか......。「異常」というか「イカン!」というか......^^;)。
>>
食糧の「小さな循環」を考えるうえで、役に立つ考え方をご紹介しましょう。 「フードマイレージ」です。
「マイレージ」は航空会社のプログラムでよく聞くと思いますが、輸送距離という意味です。「フード・マイレージ」は、食べ物の重量と 生産地から消費地までの輸送距離を掛け算したもので、「トンキロ」 という単位であらわします。
その食べ物が食卓に到着するまで、どのくらい「遠路からはるばる」来たか、を比較できる考え方です。フード・マイレージはあちこちで研究されているので、ご興味のある方は、インターネットで検索してみて下さい。
「日本」という国全体で、フード・マイレージを考えることもできます。たとえば、2000年に日本が輸入した食糧の総重量は5300万トンで、 これに輸送距離をかけたフードマイレージは5000億トンキロになるそうです。 韓国は1500億トンキロ、 アメリカは1400億トンキロ。「地産地消」「身土不二」から遠い日本の食卓がわかります。
<<
ところで、ワールドウォッチ研究所のサイトでは、ワールドウォッチ・マガジンの毎号で、1つの特集記事を無料でダウンロードできるようにしているようです。ご興味のある方はどうぞ。http://www.worldwatch.org/pubs/mag/
また、ワールドウォッチ・マガジンを日本語で読みたい!という方は、ワールドウォッチ・ジャパンへ。定期購読・バックナンバーの申し込みができます。http://www.worldwatch-japan.org/WW_JAPANESE/nihonngobanntop.html
さて、まえから私も自分で食べるもののうち「地元で作った食物の率」を少しでも上げたい、と思っていました。究極かつマンション住まいの私でもできるlocally grown food(地元産の食べ物)として、卓上でもできるというルッコラ、ブロッコリーの芽などのタネを買ってありました。ようやく出張やエコプロダクツ展などのイベントも終わったので、今日あたり種まきをしようかな、と。(^^;
何度かメールニュースにも、エコネットワーキングの会にも登場してくれているいーらいふの神宮司さんの言葉を思い出します。神宮司さんは、「街の自然エネルギー屋さん」として、ソーラーパネルの設置をしたり(JFS事務所のベランダにもつけてもらいました)していますが、その一方で、自然食品のお弁当を作っ
ています。 http://www.el-jp.com/
もともとは多摩市で営業していましたが、今年から西新宿にもお店を開き、お弁当は新宿、目黒、聖蹟桜ヶ丘、小平、新百合ヶ丘などの駅の近くでも買うことができるようになりました。(詳しくはHPに載っています)
神宮司さんいわく「野菜や穀物を作ることは、太陽エネルギーの有効な活用法のひとつなんですよ」。 http://www.el-jp.com/matiene2.htm
ホントにそうですね。太陽エネルギーは電力に変換するだけではなく、植物を育てるパワーをいただくこともできるのですね。
それから......ひなたぼっこも太陽エネルギーの有効活用ですねぇ。日が昇ったら、ルッコラのタネと一緒にベランダで陽を浴びて温まろうかな。(^^;