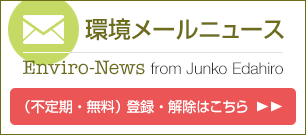エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
「私の森.jp」がオープンしました 前編(2008.03.23)
「私の森.jp」がオープンしました。
http://watashinomori.jp/
19日に、「私の森.jp」オープン記念フォーラムを開催しました。ヒノキが立ち並び、すがすがしい木の香りの中で、たくさんの方といっしょにフォーラムが開催できたことをうれしく思っています。
このウェブサイトへの思いやこれからについて、オープニング・スピーチで話したことをお伝えしたいと思います。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
皆さん、こんにちは。今日は本当にようこそいらしてくださいました。とてもうれしいです。ステージなどをご覧になって、ここに流れている空気もゆったりしているなと、きっと皆さんも思ってくださっているのではないかと思います。
この「私の森.jp」を立ち上げるに至った私の思いを、そしてこれからどんなふうに活動を展開していきたいと思っているか、少し時間をいただいて、お話をさせていただきたいと思います。
最初に少しだけ、皆さん目を閉じていただいて--でも眠ってもらっては困るんですが--、自分のいちばん大切な場所のことを思い出してみてください。小さいときかもしれません。大きくなってからでもよいです。自分のいちばん大切な場所って、どんな場所だったかな……? ちょっと思い出していだだければと思います。――ありがとうございます。
私にとっての大事な場所はどこだったかな?と思うと、たくさんあるけれど、いつも思い出すのは、保育のときから小学校4年生まで暮らしていた、宮城県のとても田舎のことです。
まわりはたんぼばかり。少し行くと森があって、ひんやりした森の空気を、いまでも思い出します。森に一歩入ると、何かちょっと怖いような感じもして、木漏れ日が踊っている、そして木立を風が渡っている、そんな森を見ていました。
大人の人たちと一緒に山に行って、流れている小川をせき止めて、フナとかドジョウを捕ったりした、そんな思い出もあります。当時、私は、まわりの子どもたちと同じように、自分のことを「おら」と呼んでいました。そんな田舎の少女時代を送って、今日、ステージに森を作ってもらって、とてもうれしく思っています。
今日は、パワーポイントのプレゼンテーションではなくて、お話を皆さんに聞いていただこうと思って、準備をしました。難しい話ではないので、どうぞ気楽に聞いていただければと思います。
むかしむかしあるところに、それはそれは美しい森がありました。
太陽の光が差し込み、その光を受けて、葉っぱが青々と茂ります。チョウチョやガが飛んできて、その葉っぱに卵を産みつけ、幼虫からさなぎ、そして、羽を広げて、空に飛んでいきます。
チョウチョやガの幼虫を餌にしている小鳥たちもいました。小鳥たちのさえずりが森に響いています。そして森には、そういった小さな小鳥たちを餌にしているオオワシや大きな鳥もいました。悠然と山の上を舞っています。
森の中には、木の芽や実、そして草を食べる小さな動物たちもいます。そして、そういった小さな動物を食べる大きな動物たちも暮らしていました。
虫たちや動物の死骸を食べる虫もいます。そして、残った骨や落ち葉を分解して土に戻す、数知れない微生物も、土の中にたくさんいました。そうして、虫や微生物が土に戻してくれた栄養を、植物がまた根っこから取って葉っぱを茂らせ、森が青々と育っていくのです。
とてもにぎやかで楽しくて、いろいろな種類の動物や、いろいろな種類の植物が、それぞれ何らかつながって、大きな森という営みを営んでいる、そんな美しい森でした。
人もまた、その大きなつながりの輪の中にいました。人々は森に入って、キノコを採ったり、木の実を摘んだり、そして、森の中にいる動物をつかまえたりして、自分たちの食べ物にしていました。病気をしたり怪我をしたときには、やっぱり森に入って薬草を探し、その力で傷を治したものです。もちろん、煮炊きや暖を取るための薪や炭も山からいただいていました。
死骸を土に戻す虫や微生物と同じように、人もこの森の中では、大きなつながりの大切なひとつの役割を担っていました。薪や炭を得るために、森の木の手入れをしましたから。
でもそれは、「森を守ろう」と思ってやっていたというより、自分たちの生活に必要な薪や炭を、いまも、そしてこれから先もずっと、森からいただこう、そのための活動だったのでしょう。
虫にしても動物にしても、同じです。別に「森を守ろう、森の循環を守ろう」と思って、いろいろなことをやっていたのではなく、与えられた自分の命を全うしよう、生きていこう--それぞれの生き物の「生きる」という営みが、いろいろな形でつながって、大きなひとつのいのちの循環を作っていたのです。これをた
ぶん、「自然の摂理」と呼んでもよいのかもしれません。
子どもたちも、森の中で遊んでいました。子どもたちにはそれぞれ、秘密の場所があって、大人にも友だちにも教えません。春のある時期になると、その秘密の場所にはフキノトウが出たり、ワラビが出たり。それを子どもたちは摘むのでした。
どんなに厳しい冬が来ても、春が来れば必ず、ここにフキノトウが出てくる。どんな年だって必ず、ここにはワラビが出る。そういった巡り来る季節の確かさ。そして大地への信頼。言葉ではなく、子どもたちは実感として、きっと感じていたのだと思います。
春になると、トゲトゲのタラノキという木のてっぺんに芽が吹きます。タラの芽です。私の田舎では、「タラん坊」と呼んでいました。これはとてもおいしいてんぷらの種になります。
トゲトゲの上のほうにつくから採りにくい。でも、だからといって、簡単に採ろうと木を折ってしまうと、どうなるでしょう? 今年は確かにラクに手に入るけど、来年から、そこにはタラの芽は出なくなってしまいます。そんな経験の中から、子どもたちは、いま欲しいものと、将来欲しいものの折り合いをどうやってつけたらいいのか、それをきっと学んでいったと思うのです。
山には木を切る人、そして木を植える人たちもいました。人手がいったん入った森は、人の手を入れてきちんと循環を支えなくてはなりません。
私はよく、「木とは50年で育つダイコンだ」と話します。ダイコンを育てるには、たくさんの種をまきます。芽がたくさん出ます。それをすべてダイコンにするのではなく、元気のいい芽を残して、あとは摘みます。摘んだ芽はつまみ菜として、それはそれでサラダやおひたしの材料として売ることができます。つまみ菜が売れるから、そして最後にダイコンが収穫できて売れるから、次の種を買うことができます。
木だって、50年かかるけど、同じです。木を植えて、育てていく過程で、いらない枝を「枝打ち」して落とします。そして、元気のいい木を残して、ほかの木を少しずつ間伐していくのです。そういう枝や木は、燃料として使われていました。間伐したなかでも、もう少し太い木は、
杭になったり柵になったり、そんなふうに使われていたのです。
すっかり成長した木を切って柱にしようというときも、余りが出ます。木はもちろん丸い形をしていますが、柱はだいたい四角だからです。そうすると、端っこは余ります。その端材も、板にしたり経木にしたり割り箸にしたり、じょうずに利用していました。もっと端っこの形にならないようなものは、チップにして紙の原料にするり。そうやって、木もすべて使い切る。これが山の暮らしでした。
ダイコンと同じです。ダイコン1本を買って、すべてダイコンおろし、すべてサラダにする、ということはきっとないでしょう。ダイコンの首のあたりは、ぶり大根のような濃い味つけの料理が合います。真ん中はあっさりしているから、サラダにしたり、薄味の煮物にしたり。そしてシッポのところはダイコンおろしに、ダイコンの皮はキンピラに、葉っぱは菜飯やお漬物にしたり。
ダイコン1本すべて使い切るのと同じように、木も1本すべて使い切っていました。だから、山での暮らしが成り立っていたのです。
ちなみに、人もまったく同じだと思うのです。日本には、「もったいない」というすてきな言葉があります。「もったいない」の「もったい」って何だろう? そう思って辞書を調べたことがあります。何がないとき私たちは「もったいない」と言うのだろう?と。
「もったい」にはいくつかの意味がありますが、そのうちのひとつに、「そのものの本質、命」というような意味があります。そのものの命が最後まで全うされずに終わってしまったとき、私たちは「もったいない」と思うのでしょう。
ですから、木のカケラも端材も間伐した木も、すべて使い切って、切った木の「もったい」を活かし切る--そういった素晴らしい生き方を、私たちはしていたのではないかと思います。
人間にだって、いろいろな人がいます。そのときに、ちょっと変わった人も、昔はごく普通に、村の中で生活していました。いまだと施設に入れられてしまうような、ちょっと変わった人たちも、それなりの役割を村で果たしていたような気がするのです。
山で木が育ち、それを山に住む人たちが、切ったり植えたり手入れをして、薪や、そのほか必要なものにして、町に住む人に売っていました。町の人たちは、必要なものを山から得る代わりに、山にお金を戻していました。だから山の手入れをずっと続けることができていました。たぶん、そんなにぜいたくではなかったと思うけど、確かな、幸せな時代だったのではないかと思います。
ところが、いつのころか、灰色の男たちが、森にも町にもやってくるようになりました。灰色の男たちは、山に住む人や町に住む人の耳元に、「お金こそが大事なんだよ」「どんどん成長するべきなんだよ」と吹き込みます。
灰色の男たちの言葉に耳を傾けた人たちは、だんだんと、それまでの暮らしでは飽き足らなくなってきました。そして、「比べる」ことをするようになりました。人と比べたり、すごく大きなものと比べて、だから自分は幸せではない、そんなふうに思うようになってしまったのです。いつも満ち足りていない不安やいらいら、欠乏感を抱えた、そんな人たちが、町にも山にも増えていきました。
「お金こそが大事だよ」と吹き込まれて、信じてしまった人たちは、お金にならないことはやらなくなってしまいました。かつては、山でも町でも、「稼ぎ」という生計を立てるための仕事と、本当の意味での「仕事」という、役に立つことを、分けて考えていました。
もちろん稼ぎも大事だけど、本当に村のためのこと、たとえば村の道の手入れをするとか、助け合いをするとか、そういったことを大事にしていたのに、「お金こそが大事だよ」ということばを信じてしまった人たちは、稼ぎにならないことをしなくなってしまいました。
村の道の手入れをする人がいなくなり、お互いに助け合っていた暮らしもなくなってしまいました。お金がすべての価値判断になって、安ければ安いほどいい、となってしまったのです。本当は、物事を見るときに、いくつかの判断基準があるはずなのに、値札しか見ない--そういった人たちが増えていきました。
そうしたときに、「外国のほうが安くできるじゃないか」「外国の木を持ってきたらいいじゃないか」「外国の紙を輸入すればいいじゃないか」「木なんて、途中で腐って、手入れが大変だ。プラスチックにしたらいいじゃないか。ずっと長持ちして、手入れしなくていい」というふうになっていきました。そうして公園の柵も、木ではなくプラスチックででき、木のように見せかけられた擬木の柵に替わっていきました。
でも、山は、そういった変化についていけませんでした。だって、山はどんどん成長することはできないからです。山は山のペースで、自然のペースでしか成長することができません。
それに、お金で測れないものが大事だったのに、それが、価値がないものだと考えられるようになってしまったからです。星の王子さまだって、「本当に大事なものは目には見えないんだよ」と言っています。でもいまでは、町の人も山の人も、「値札がついていないものは大事じゃないんだよ」と言うようになってしまいました。
確かに、外国から運んでくる木材は、一見安く見えます。でも、それはなぜかというと、人ではなく、自然が長年かけて育ててくれたからです。自然がどんなに手間をかけたか、それに対してはまったくお金を払っていないからです。そして、労働力の安いところから、船でその木を運んでくるために、どれほどのエネルギーの枯渇を引き起こし、二酸化炭素を出しているか--その費用を全然計算に入れていないから、外国からの木は一見安く見えるのです。
国産材は、一見高く見えます。でも本当は、手を入れ続けることで、森の循環を守り、命のつながりを守り、日本の国を支えているのです。その大切な役割には値札がついていません。実際には、木の伐採と輸送のコストだけで判断されてしまうと、国産材はなかなか外材に太刀打ちができませんでした。
灰色の男たちの影響力はとても強く、どんどん成長することができない森は、見捨てられていきました。みんなが安い外材を使うようになり、薪や炭に替わって、石炭や石油やガスを使うようになって、そうやって、町の人の暮らしのなかでお世話になる機会が減るに従って、町の人たちのお金も思いも、森には戻らなくなってしまいました。
かと言って、町の人たちの思いが、外国の森に行ったのか、というとそうではありませんでした。日本のための輸出材を伐採する現場に、人々が思いを馳せることは、ほとんどありませんでした。または、日本に輸出をするための木を育てるため、苗木を食べられたら困るからと、野生動物をすべて殺してしまう目的で、毒入りニンジンがまかれている、そんな現場があることにも、私たちは、思いを馳せることはほとんどありませんでした。
または、薪や炭に替わった石炭や石油という化石燃料を生み出すために、何千万年も地球がかけてきた時間に思いを馳せる人もありませんでした。ただ、値札だけを見て、「安いから」「便利だから」と言って、どんどんと使うようになったのです。
それは、でも、人々が悪いと言うよりも、すべてが加速度的に忙しくなって、つねにせかされるような生活になってしまったため、立ち止まって、大切なことに思いを馳せる、そんな時間すら取れなくなってしまったからなのです。
大事なつながりを保つためには、目に見えない、取るに足らない、でも大切なことがたくさんあります。そういったものはすべて、雑用だとか、雑事だとか、雑役だとか、雑念だとか、雑談だとか、「雑」という言葉をつけられて、価値がないものだと思われるようになりました(今日、広辞苑で、「雑」がつく言葉がいくつぐらいあるかと思って調べてみたら、170以上ありました!)それは価値がない、意味がないと、私たちは思うようになってしまったのです。
そうして、人々の思いやお金は森から遠ざかってしまいました。手入れもされなくなり、木が育っても、切って使ってもらうことができない--そんな森は、日の光も入らなくなり、虫も草も微生物も、みんな姿を消してしまいました。命の営みも、自然のつながりも、息も絶え絶えになってしまったのです。
町と森をつないでいた道も使われなくなってしまい、荒れ果てていきました。いつしか、かつて道があった、かつて森と山は町とつながっていた――そのことすら、みんな忘れてしまったのでした。
では、一方で、町の人たちは幸せになったのでしょうか。気がつかないまま、森とのつながりが切れてしまった町の人たち。自然のリズムや自然のペースと切り離されて、人間だって本当は動物なのに、人工的なペースで生きざるを得なくなってしまった町の人たち。「経済成長という自転車をこぎ続ける力を少しでも弱めたら、倒れてしまうよ」と脅され、集団的なその強迫観念に、「何のためにやっているのだろう?」と、みんなうすうすそう思いながらも、一生懸命自転車をこいでいる町の人たち。
山は、人々が来ていたころのにぎやかさや、子どもたちの笑い声を恋しく思い出し、真っ暗な中でため息をつきました。山の人たちも、炎天下の下草刈りや間伐は確かに大変だけど、でも自分が育てた木を切って、そして町の人たちが使ってくれる、その誇らしさと喜びを思い出して、ため息をつきました。
町の人たちも、自分たちがお金やスピードや効率の代償に何を失ったのか、それすらわからないいら立ちを感じ、どうやったら、時間を止めどなく切り売りするようなこの生活から、本当に地に足をつけた、幸せと自分自身を実感できる生活に変えられるのだろう……そんな思いでため息をついています。
でも、明けない夜はない、といいます。「冬来たりなば春遠からじ」。
そう、そのような、森にとっても、森に住む人たちにとっても、町の人たちにとっても、本当には幸せではなかったかもしれない、そんな時代から、少しずつ、いろいろな変化の兆しが出てきている--それが「今」ではないかと思うのです。
( つ づ く )