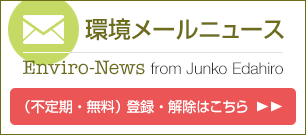エダヒロ・ライブラリー環境メールニュース
内藤正明先生「自然共生的な持続可能社会への転換を目指して」 (2009.05.23)
滋賀県が2008年3月に「持続可能な滋賀社会ビジョン」を発表しました。
http://www.pref.shiga.jp/d/kankyo/sd_shiga.html
2030年に温室効果ガスを1990年比50%削減するという、とても積極的なビジョンで、そのために各セクターがどのように取り組んでいくべきかを示しています。
昨年暮れに、この滋賀ビジョンの策定に深く関わっていらっしゃる内藤正明先生と滋賀でのパネルディスカションでご一緒させていただきました。そこでお話しになった問題意識などにとても重なるものを感じていたところ、「地球環境ガバナンス」「環境文明」などにお書きになったものを元に再編なさった
原稿を送って下さいました。
文明論、技術論も含め、いろいろと考えさせてもらえる内容だと思い、内藤先生のご快諾を得て、ご紹介します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ここから引用〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「自然共生的な持続可能社会への転換を目指して」
―技術や社会のあり方はどう変わるかー
琵琶湖環境科学研究センター長 内藤 正明
(佛教大学教授、京都大学名誉教授)
○人類生存の危機
21世紀に入って世界は急激に不安定化し、まさに一つの世界パラダイムが、その限界に達して崩壊し始めたように見える。その危機は“社会・経済、文明、環境”など「物質的」、「精神的」両面で現れようとしているが、それらは個別に起こっているのではなく、すべてが複雑に連動して生じている。その中でも深刻かつ象徴的な物質面での現象は、“地球環境の崩壊と資源の枯渇”だといえよう。
最近の地球環境に対する様々な研究結果は、人類の生存基盤である地球環境の破滅的状態が数年オーダーでも起こりうる可能性を示唆している。これに対して、いまはもう専門家内でも表立った批判はほとんど聞かれない。たった7年前の京都会議の時点では、地球環境問題そのものにまだ懐疑を表明するグループがかなりあったことを思うと、その状況の悪化は驚くばかりである。
問題は、その間に様々な“地球にやさしい”といわれる行動促進や技術開発などの努力がなされてきたが、顕著な効果は見られないことである。その最大の理由は、温暖化の主な原因物質であるCO2こそまさに、20世紀の科学技術が全面的に依存している化石燃料の消費に由来するものであるためである。
それゆえ、環境保全技術も含めて化石燃料に依存するいまのあらゆる技術は、基本的に"地球にやさしく"はありえないことにある。例えば、ガソリン自動車が電気や水素のエンジンに転換すれば問題が解決するようにいわれているが、その電気や水素を創るための一次エネルギーについて言及されることは少ない。結局は、石油か原子力か自然エネルギーかの選択の問題であり、末端のエンジン技術の問題ではない。結局は、石油に代わる他の一次エネルギー源がありうるかどうかの議論になるが、結論的に現在のエネルギー消費レベルを代替することは困難であることは計算すればすぐに分かることである。
このような意味で、温暖化問題こそ今日の技術文明に対する最終的な警告とも思われる。先の洞爺湖サミットでは世界全体が石油消費を中期的には半減し、工業国では80%もの削減の必要性が提唱された。まさに石油文明の終焉である。文明の衝突や宗教的対立と見えるものも、その背後に生存基盤である資源と自然の危機的状況がある。
○危機をもたらした原因
人の生存さえもが危惧されるような事態を招いた原因は何か。これについては、特にこの世紀を特徴付ける“巨大技術と産業”にあるとして、そのあり方が大きな議論となってきた。ところがこれまでの日本の方向は、これまでの産業社会を前提とする、“business as usual”と称されるものである。多くの予算を注ぎ込んで実施してきた高度技術の開発にも拘らず、これまでのデータで明らかなとおり、技術先進国を自負する我が国でも、この種の対応はほとんど目に見える効果をもたらしていない。このことは、単に技術、産業というハードの側面に対する、いわば対症療法では問題は解決しないということの示唆であろう。
さらに今日の危機のもう一つの側面である「社会・人間への影響」として、“高度な科学技術と経済至上主義がもたらした副作用としての心の崩壊”がある。今日の工業先進国では、あらゆる技術とその製品に囲まれている為に、自分の暮らしが誰かに支えられているという感覚は生まれる余地がない。スーパーの棚で何でも手に入り、蛇口をひねれば水が出てくるという状況で、自然の恵みを実感することが難しいだけでなく、他者の恩恵を思う意識もなくなるだろう。このような利便や豊かさこそ、技術がこれまで目指してきた目的であったのだから、それが目的を達したというべきであろう。
他者の力や自然の恵みに代わって必要になったのは「お金」である。自らの労働の対価(と思っている)金さえ持っていれば、あらゆるものが手に入る状態では、感謝や畏敬などという心はもはや必要としない。また、このような技術に大きく支えられて育った人間が、人と力をあわせること、我慢することなどもできないといわれるのも、技術の恩恵がもたらした当然の副作用と考えられる。
○新たな社会のための技術
人類全体の幸せを、この限られた地球の中で達成するための技術とはどのようなものか。そもそも技術とは、一部の人に「豊かさ」をもたらと同時に、様々の「副作用」を、特に弱者にもたらす。そのことへの反省として、20世紀型の大規模先端的技術とは異なる技術概念がこれまでにも提起されてきた。それらを要約すると、
「中間技術〔intermediate T.〕」(E. シューマッハ)
途上国や工業国の地方社会にとって有効な、土着技術と近代技術の中間の技術であり、“地域の資金、雇用、文化、対応能力”で受け入れが可能なもの。これまでの途上国技術援助の失敗に対する反省から生まれた提案。
「適正技術〔appropriate T.〕」(ITDG initiated by Schumach)
市民管理可能性、生態的健全性、資本節約的、労働集約的、地域資源活用型、などの特性を持つ中間技術の発展概念。
「適正高度技術〔appropriate advanced T.〕」
高度技術の担い手が適正技術を開発し、大量生産して世界に供給するもの。
「代替技術〔alternative T.〕」
技術はそれを受容する社会の体制と不可分であるとの認識に立つ。したがって、大量生産・消費の物質文明と連動して進化してきた現代技術と相対する特性を持ち、地域の自給的生活、共同体的社会経済構造などを前提とする。そのため、「ユートピアン・テクノロジー(by D.Dickson)」とも呼ばれる。
さらにその技術内容を挙げると、「身の丈のローカル技術である、市場競争から免れる、自立的である、主に生物・生態系を利用する」といったものである。このように、市民が力を合わせて、かつ自然の力に依存する技術は、自然のリズムに合わせてその恵みと脅威を実感として感じさせるだろう。そのことは、いまの社会が直面する「人と人」、「人と自然」の共生に関する危機的状況を解決するにも有効であろう。
○西洋的世界観からの脱却
そのような物心両面での危機的な状況を回避するには、個々の対症療法ではなくそれが拠って来る社会の価値観そのものの転換なくしては不可能であろう。それは結局、これまでの「無限世界観」の下に、人間がその限りなき欲望を充足することが正義であるとする価値観から、「世界は有限」であるという世界観の下での節度ある生き方を是とする価値観への転換ではなかろうか。
このような世界観の転換は当然、倫理観という行動原理の大きな変革を要求し、その結果として産業や経済から文化まで社会のあらゆる側面の大転換にも及ばざるをえない。その変革の過程と将来の社会像を描くことが、いまの最大の課題である。
Catton and Dunlap(1980)は既に20余年も以前に旧来の社会学を強く批判し、新たな環境社会学を提唱した。その主張の中心は、これまでの西洋的世界観からエコロジカル世界観へのパラダイム転換である。つまり、前者が“人はあらゆる生物を支配する存在で、みずからの運命を自己決定し、その歴史は進歩を続けるものである”とするのに対して、いまや新たなエコロジカルパラダイムとして、“人間は地球エコシステムの一員として相互依存する存在で、自らの運命は環境との因果関係に依存し、その歴史は自然の法則に大きく支配されるものである”とするものであった。
そもそも人間が自然をどのように認識するかについては、すでに環境問題が顕在化し始めた60年代からも、「キリスト教的自然観」と「仏教、アニミズム的自然観」が対置され、それぞれにおける“人と自然の位置づけ”についての議論が高まった。ここでは、なぜそのような「世界観」がそれぞれに形成されたかを自
然科学的な視点で要約してみよう。
○東西の世界観の由来
西洋が「世界」としたのは、神の法則に支配されたコスモス(宇宙)のことであり、地上の自然界はカオス(混沌)と認識した。そして、その地上の混沌は糺さねばならないものと考え、それを神の法則に則って文明化するのが人間の役目とした。ここに人間が自然より一段上の存在とする理由がある。一方、東洋的または仏教的といわれる世界観では世界を地上に限定していて、地球生態系が対象の全てであり、宇宙は対象系外としているように思われる。それを仏典から証明することは門外漢では難しいが、熱力学の第二法則(「エントロピー増大則」)を鍵として思考した先例がいくつかある。それを参考に筆者の解釈を加えて整理してみよう。
もし「宇宙全体を対象系」とした場合には、エントロピー(エネルギーの汚れ=熱と物質のrandomness)は一方的に増大し、最終的には系全体は熱的死(heat-death)に至ることになる。これは、世界が誕生から消滅まで直線的であるとした、キリスト教的世界観に一致するように見える。一方、永遠の生命の輪廻と物質の循環を説く仏教的世界が成り立つのは、「地球を閉じた系」とした場合である。また、「不生不滅」、「不増不減」はそれぞれ「質量保存」と「エネルギー保存」の法則に対応すると解釈すれば、これらも閉じた系内で(それを宇宙とするか地球とするかは問わず)成り立つ法則であるが、問題は「不浄不垢」にある。エントロピー増大則によれば、地球閉鎖系内でもエネルギーの汚れ(質的低下;エントロピー増大)は一方的に進行する。ただし、「不垢」が成り立つ条件は系外からの太陽の恵みであり、それが垢を清め(エントロピー減少させ)て、一定を保ってきた。ここに、太陽をすべての元として崇める一つの理由があるのだろう。
なお、佛教などでいう世界は、魂の次元(彼岸)のことであり、このような現世(此岸)の解釈を言っているわけではないという、佛教専門家のご指摘を受けた。ということで、上の解釈はあくまで工学屋の思いつきと、ご放念頂くべきかもしれない。
○人類持続のための社会づくり
地上の混沌(地球生態系)を時に的に整えることを目的として発達してきた西洋近代科学が、今日の地球環境の危機と大いに関ることは否定しがたいだろう。また特に宇宙の「無限世界観」の下では、広大無辺の宇宙に向けて欲求を拡大しても、それは無限のフロンテイアを開拓することであり、他者の領域を犯すことにはならない。したがって、競って活動を外部に拡げることこそが、社会全体を向上させる動因であるとの考えに至るだろう。
一方、仏教のみならずア二ミズムの世界観で、もし世界を地球生態系に閉じたとすると、「人は自然の一部」として自らが生きる規範を、生物・生態系の法則の中に見出すこととなろう。その法則の中心は「循環」と「共生」である。これは、質量保存、エネルギー保存、およびエントロピー増大則に矛盾せず、さらにガイア論にも示唆される生態系のネットワーク構造の生物的法則とも一致する。ということから、地球環境危機の克服は、「競争原理」から「共生原理」への転換に求めるべきではないかという筆者の主張に繋がる(表―1)。
○持続可能社会の模索
いま地球環境の危機を克服する人類持続のための方途が模索されているが、その方向は世界的にも、我が国の中でも大きく二つに分かれている(表―2)。一つはこれまでの石油に支えられた工業文明の力を信じて、無限発展を指向する立場である。もう一つは、地上だけを人の生きる世界とし、その限られた世界の中で“人は生物の一種”であることを受け入れて、生態学的法則に従って循環共生社会を再構築する立場である。
後者には、将来世代や生物を含む生命全てとの地球倫理がその背景にある。このような理念に立って、人類持続の新たな社会を構築する試みが、世界の各地で見られる。これは何故か西洋社会で先行しているが、恐らく自らが作り上げてきた西洋近代文明に対する危機意識が動因となり、仏教的な有限世界観へとスピリチュアルな転換を求めた人達が多く生まれたことによるものか。その具体事例としての“世界エコビレッジネットワーク”は、世界中のその種の試みを繋ぐ大きなネットワークであり、その活動は年々急速に拡がりつつある。
また、30年も前に「佛教経済学」を唱えたのもドイツのシューマッハである。そして、“スモール・イズ・ビューテイフル”に繋がる新たな技術理念は、その後の技術観を大きく変えた。それに対し、日本は本来持ってきた仏教的世界観が、まだ現実社会を動かす動機付けとはなっていない。
その理由は、この60余年を一貫してアメリカ型文化の信奉者として、西洋近代型の無限発展社会を追い続けてきたためと思われる。明治維新と第二次大戦後の西洋科学技術に対するトラウマがいかに強かったかということであろうか。しかし、既に社会の崩壊ともいうべき状況に自ら直面してきた地方都市や村落が、伝統的な世界観とあいまって、新たな自然共生的社会に可能性を求めて、それへの転換に向けて動き始めた。いまこそ、シューマッハが提唱した“もう一つの技術”に連なる「適正技術」、「地域技術」などの理念を、この地球環境危機に際して改めて再認識するときではないか。
○自然共生社会への動き
そこでいま、「産業技術」ではなく「社会技術」を中心に、都市工業系ではなく地域コミュニテイーにおいて環境文明社会を構築するための活動が、まだ局所的ではあるが各地で見られ始めた。我が国では、県スケールの者としては「滋賀ビジョン」が唯一のものとして、世界にも評価されている。その概要は以下の通りである。
(1)滋賀ビジョンづくりの背景
真に持続可能な社会の姿を模索しようとする動きが各国、各地域で起こり始めたが、洞爺湖サミットに向けて作られた、日英共同研究プロジェクによる“Country Scenarios toward Low-Carbon Society”報告書では、22カ国のシナリオが集約されている。その中で、地方レベルでは唯一滋賀県のそれが取り上げ
られ、その概要が日本国のものと同等のスペースで紹介されている。
ではなぜ滋賀だけがこのような社会像を提起しえたのか。それはいくつかの条件が揃ったことによるが、第一に琵琶湖という大事な環境資源を持つために、これまでも環境先進県としての先駆的な政策を実施してきたことである。この度も、「真の持続可能社会を滋賀発で全国に発信したい」という知事の強い意向もあって、県と筆者らの研究会が議論を重ねた。その結果を踏まえて県の「持続可能滋賀ビジョン」として策定されたが、それは「環境基本計画」や「基本構想」とも並ぶ重要な役割を持つものとして位置づけられた。
(2)滋賀ビジョンの特徴
滋賀ビジョンの特徴はどのようなものかを、筆書の視点で要約してみよう。
第一に、それは単に地球環境危機の進行を防止する「緩和策」ではなく、危機が来ても「適応」して生き残れる社会である。“なぜ滋賀だけが率先してやるのか、また地球全体にどれだけ意味があるのか”という問いには、いまや“滋賀が生き延びるため”という答えが現実味を帯びてきた。
第二は、“それではエゴではないか”という批判に対しては、今の危機状態では、各自がその救命ボートを自分たちで設計する以外にない。ただし、そのためのノウハウは誰にでも提供するということである。
弟三は、このために滋賀ビジョンは、国が提唱するような巨大先端技術型ではなく、滋賀の自然、社会、技術、文化などに立脚した「自然共生の地域自立型」に軸足を置いていることである(図-3)。それは、地方や途上国のモデルとしても普遍性があり、また先に述べた地球生態系の本質にも則った、脱石油社会の唯一の可能な姿であるからである。
第四は、目指すビジョンの特徴から、それは単に温暖化だけを視野に入れた「低炭素社会」ではなく、「石油ピーク」や各種の資源枯渇も考慮した「脱資源型社会」、さらにこのような資源と環境の危機をもたらした、大量生産およびそれと表裏一体となったグローバルな経済構造や社会の崩壊現象の回避も視野に入れた「持続可能社会」というべきものと言える。また、そうでなくては脱温暖化さえ不可能である。
いまその具体化に向けていよいよ動き始めている。それを人類生き残りの貴重な実践例として、その実現に各界、各方面からの支援を切望するものである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜引用ここまで〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
滋賀の動きに注目〜!ですね。
あちこちの地域から、こういう動きが広がっていけば、と願っています。
今から、ホテルを出て、アテネの波止場へ移動します。ギリシャの海はどんな色をしているのかな〜? 楽しみです。(^^;