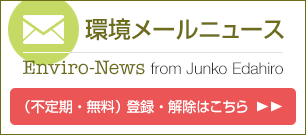エダヒロ・ライブラリー講演・対談
パネルディスカッション「GNHと未来社会への構想」 その1
コーディネーター 草郷孝好(関西大学教授)
パネリスト 枝廣淳子(環境ジャーナリスト)
西川芳昭(龍谷大学教授)
ダショー・キンレイ・ドルジ(ブータン国中央政府情報通信省次官)
パネルディスカッションⅠは、GNH(国民総幸福)を国の目標として掲げているブータンのダショー・キンレイ・ドルジ氏による基調講演「GNH(国民総幸福)に喚起された開発のパラダイム」を受ける形で、2人のパネリストによるプレゼンテーションをベースに約2時間にわたって行われました。
<プレゼンテーション>
枝廣淳子:私は十数年前から環境問題に取り組む活動をしていますが、アメリカのアル・ゴアの『不都合な真実』の翻訳をしたり、特に3・11以後、日本のエネルギー政策をどうすべきかを検討するために政府が資源エネルギー庁の中につくった委員会の一員に加わったりしてきました。そうした活動の中で特に私が強く感じたのは、地球温暖化やオゾン層の問題、あるいは化石燃料や原発に依存したエネルギー消費といった問題に個別に取り組んでいるだけでは根本的な問題解決にならない、ということでした。
環境問題やエネルギー問題は、経済成長を前提とすることから起こっています。その前提条件を考え直し、経済や社会の仕組みを根本的に変えていかなければならないのではないかと強く思うようになったのです。そのためにつくったのが「幸せ経済社会研究所」で、経済成長あるいはGDPの拡大を目標とした経済のあり方ではなく、人間の幸福を目標とした経済のあり方を模索してきました。
そういう活動をしているときに出会ったのがブータンから発信されたGNHという考え方でした。このGNHこそ、日本の未来の社会を考えるうえで避けて通ることができない考え方だと思います。その理由の1つは、日本の経済成長やGDPの拡大と、それに必要とされるエネルギー量はほぼ相関していますが、そのエネルギー量を何によって確保するかという議論は常になされているのに、そもそもどのくらいのエネルギー量が必要かという議論は二の次になっていて、いつも議論の対象から外されているということです。
日本は、今、急激な人口減少社会に向かっています。2030年までに人口が20%減少するという試算も出ています。にもかかわらず、政府や経済界は相変わらず、現在と同じ経済成長率を前提とした経済規模の維持を追求しています。人口が減少するのに、現在と同じエネルギーを確保しようとすれば、コストがかかりすぎて、いずれ経済自体が立ち行かなくなります。
そこで私が提唱しているのは、たとえば経済成長率をゼロとすることです。経済成長率をゼロとしても、日本は人口が減少していきますから1人あたりのGDPは増える計算になります。エネルギーは、あくまでもツールであって、どれぐらいのエネルギーを使うかということは、すなわち日本がどういう社会をつくりたいのか、国民がどういう暮らしをしたいのかということと深く関わっています。それによって、必要なエネルギー量は変わってくるわけです。まず、そこから考える必要がある。つまり、もっと長い時間軸で日本の未来を考える必要があるということです。
私たちが求めているのは、経済規模の拡大ではなく、一人ひとりの国民の幸せだと思うのです。本来、人間は幸せになるために経済生活や社会生活を営んでいるのであって、私たちはその幸せの指標というものをあまりにも考えてこなかったと思います。そこにブータンからGNHという考え方が提案され、私たちは人間の幸福というものを考えるきっかけやツールをブータンからもらったと思います。
日本の人々、特に若い人たちは、経済的な豊かさより、自然とか家族とか自由な時聞を大切にする価値観を重視する傾向に変わってきています。行政においてもGNH的な幸福の指標をつくっている県や市町村が増えていますし、それは世界的な傾向でもあります。地球の資源やエネルギーに限界がある以上、経済成長の追求はもう不可能であって、むしろ人間の幸福は何によって成り立つのか、その測り方はどのような測り方が望ましいのか、そうした価値観の転換こそが、今の日本の社会、そして未来社会の大事な課題であると思います。
西川芳昭:私は内発的発展の事例を2つ、ご紹介したいと思います。これは、今日のテーマであるGNHとも非常に共通する部分があると思います。2つの事例は、九州の大分県から始まった「一村一品運動」といわれるもので、自分たちの町や村をどのように存続させていくかということから始まった取り組みです。
大分県の「一村一品運動」というのは、人をひきつける場所づくりという地域振興策で、1979年、当時の平松大分県知事が提唱した、ムラ起こし、マチ起こし運動です。その特徴は、自主独立、創意工夫、人づくりで、ローカルにしてグローバルであることをめざしています。
まず、湯布院の事例です。湯布院は「一度は行ってみたい温泉」で有名になりましたが、そこのシンボルは由布岳です。湯布院の人たちは、マチのどこからでも、マチのシンボルである山が見えるマチづくりをしたいと考えました。そのために、高層の大きなホテルはつくらないということを決めました。高度成長期には、どこの温泉地でも歓楽的な温泉街をつくることがはやったのですが、湯布院はあえて、それと反対のことをやったわけです。それでも湯布院は、現在、年間400万人の観光客が訪れる温泉地として独自の発展をしています。
湯布院の人たちは、どんなことを考えたか。歴史を振り返ると、高度成長期には、都市部へ水と電力を供給するためにダムの建設をしようとしました。ところが、湯布院は盆地なので、ダムを建設するとマチ全体が水につかつてしまうので、マチの人たちは、ダム建設に反対して、自分たちのマチを守りきりました。その後、ゴルフ場をつくろうという話も出ましたが、これにも反対してゴルフ場をつくらせませんでした。この湯布院の考え方の背景にあるのは、ドイツの考え方で、「100年先のマチづくり」というものです。自分たちの住み心地のいいマチづくりと、自然環境を守りたいということで、40年間、闘い続けているわけです。
もう1つの事例は、「いいちこ」という焼酎に関する事例です。「いいちこ」は最も売れた時期で400億円の売り上げがありました。沖縄の「泡盛」が20数社で200億の売り上げなのに対して「いいちこ」は1社で400億ですから、いかにすごいか、おわかりいただけると思います。
この「いいちこ」も、「一村一品運動」として、自分たちの資源を使ったモノづくりをしたわけです。三和酒類という、もともと別の3つの会社が、日本酒の消費が落ちてきたので新しい商品を開発しようと焼酎づくりを始めたのですが、そのとき使った材料は100パーセント、オーストラリアから輸入した大麦でした。その大麦に地域独自の水を使って焼酎をつくり始めたのです。今は国産の大麦を使っていますが、国産の大麦が使われるようになったのにも、わけがあります。これは、国が減反政策を進めたとき、県は米に代わって大麦の栽培に切り替えたのです。焼酎の醸造に適した品種を国の研究機関が開発したので、それを県が取り入れたわけです。
そして、この会社は市場価格より高い価格で大分県の農家から大麦を買い上げ、「西の星」という焼酎を開発しました。つまり、この会社は「いいちこ」というブランド品をもっているおかげで、利益を地域に還元しているわけです。そのことによって、地域の誇りである、100パーセント地元産の大麦と水と空気を使った焼酎をつくっているということです。
「一村一品運動」における地域資源の活用は、単なる特産品づくりではなく、最終的な目標としては、地域資源の活用を認識したうえでの人材開発を重視しています。それぞれの人が今のシステムを認識したうえで、自分がどう行動できるか。それを大切にすることによって、この運動は今も生き続けています。
最後に概念としてのまとめをしたいのですが、日本の農業や農村開発をするうえでは3つの考え方がありました。1つは、生産の効率を上げる経済的価値の追求。2つ目は、生命と環境の農学という生態的価値観の追求。3つ目は、生活の農学です。
今後は、この3つを総合的に考えていく「場の農学」が大切だと思います。その地域に生きる人たちが、いろいろな形で参加することができ、しかも、それぞれの人たちが望む総合的価値を追求することができるような農業、農村が必要で、そういう可能性のある農村は日本には無数にあると私は思っています。もちろん、経済的規模では、わずかな部分だと思いますが、事例の数や関わっている人の数という意味では、日本全国にたくさんあると思います。そこから、私たちは今の社会のシステムを変えていく可能性があると思います。たくさんある事例を、どうGNHの枠組みの中に位置づけて、未来に向かって発信していくか、ということが課題だと思います。[その2につづく]