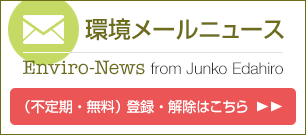エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
tragedy of commons
漁場の崩壊から温暖化問題まで、様々な環境問題に共通する構造として、tragedy of commonsという言葉を聞いたことがありますか?
tragedy とは、悲劇や惨事のこと。commonsはcommonの複数形です。commonの形容詞は「共通の、共有の、公共の、公の」という意味です。名詞では「(地域共同体が利用する)共有地や公園、広場」という意味があります。
tragedy of commonsは「共有地の悲劇」と訳します。この概念は、1968年に生物学者ギャレット・ハーディンが『サイエンス』誌に発表して、知られるようになりました。
例えば、池の魚釣りを考えて下さい。池が自分の敷地内にあったら? ほかの人は入ってきません。いつまでも釣りを楽しめるように、少しずつ釣ったり、釣っても戻したりするのではないでしょうか?
一方、もし誰でも行けて、所有者のいない「みんなの池」だったら?
「今度来たときに魚がいなくなっていたら困る」などと思って、できる限り釣ってしまおうとする人も多いのではないでしょうか。
釣り人たちがみんなそう思うと、どんどん釣ってしまいます。一網打尽にしようと、こっそり底引き網まで使う人も出てくるかもしれません。
池はあっという間にからっぽになってしまうことでしょう。
このように、誰でも好きに利用できる共有地や共有資源は、過剰な利用や乱獲によって、崩壊したり資源が枯渇してしまう、という事態が「共有地の悲劇」です。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか? 釣り人がどんどん釣る場合の「利益」は釣り人本人のものになりますが、そのために池が空っぽになったときの「被害」は、その池で釣る釣り人全員が受けることになります。
つまり、個人にとっては、増やした釣果だけ利益が多くなりますが、池の漁場崩壊という損失は釣り人全員に分散するため、個人の経済的利潤のみを追求すると、「釣果を増やすことの方が合理的」という判断になってしまうのです。
「自分の池」だったら、利益も被害も、もろに自分だけに返ってきますから、「全部釣ってしまう」というばかなことは起こらないでしょう。
これは温暖化問題にも当てはまります。私たちの「エアコンの効いた部屋で快適に過ごしたい」「自動車で便利に移動したい」という考えは、個人の利益という点では合理的な判断かもしれませんが、みんなが同じように考えて、同じように行動すれば、その結果、温暖化が進み、結局全員がその被害を受けることになります。
このような共有地の悲劇が起こらないようにするには、共有地の利用に対する料金や課税の設定が考えられます。釣り人から入漁料を取るように、CO2の排出に対する炭素税の導入などは、共有地の悲劇という起こりがちな構造を防ぐための手段ともなるのです。