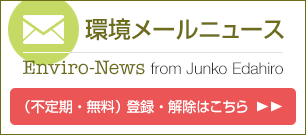エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
ハーマン・デイリー氏に聞く 「定常経済」へ、いまこそ移行すべきとき(出典:「世界」2014年8月号)<その1>
出典:岩波書店「世界」no.859 2014年8月号
聞き手:枝廣淳子
Herman Daly
1938年生まれ。メリーランド大学公共政策学部名誉教授。環境経済学の開拓・確立者の一人。もう一つのノーベル賞と呼ばれる「ライト・ライブリフッド賞」を1996年に受賞。地球環境問題の解決に向けて貢献した個人や団体に贈られる「ブループラネット賞」の今年度の受賞者。著書に『持続可能な発展の経済学』など。
■「不経済な成長」
―温暖化や生物多様性の喪失など、地球はもうもたないという状況になってきたのに、日本も世界も「もっと経済成長を」です。
「経済成長」という言葉には2つの意味があります。
1つは、人やモノを含む経済そのものが物理的に大きくなるという意味です。「経済」の成長ですね。
もう1つは、費用よりも便益のほうが大きい、「経済的な」成長、実質的にプラスになる成長という意味です。
「経済」の拡大が「経済的」とは限りません。「拡大すること」の費用より便益が大きい場合もあれば、逆に、費用のほうが大きい場合もあります。「経済」の成長と「経済的な」成長はイコールではないのに、みんなこの2つをごっちゃにして、「経済成長は良いものだ」と考えているのです。
かつてとは違って、今では、環境問題を含む、経済の成長のための費用のほうが、生み出される便益よりも大きくなっており、「不経済な成長」になっていると考えています。
企業でも、生産を拡大する限界便益よりも限界費用が大きくなる時点で、拡大をやめますよね? 費用が利益を上回るのにどこまでも生産を拡大する企業はないでしょう?
同じように、経済成長の限界便益よりも限界費用が大きくなった時点で、経済成長を続けるのはやめて、「定常経済」に移行するべきなのです。
「定常経済」というと、経済が止まってしまう、死んでしまうというイメージを持つ人もいますが、そうではありません。今と同じように活発な経済活動が繰り広げられ、成長する企業もあれば衰退する企業もある。しかし、経済の規模自体は大きくなり続けない、ということです。
―定常経済という考えはどこから出てきたのですか?
私も最初は、成長経済を信奉する経済学者だったのですよ。今も多くの人がそうであるように、「経済成長こそが、さまざまな問題に対する主な解決策だ」と信じていたのです。その私の考えを変えた要因はいくつかあります。
1つは、古典派経済学を勉強したことです。ジョン・スチュアート・ミルをはじめ、古典派経済学者たちは「好むと好まざるとに関わらず、将来は定常経済に向かっていく」と信じていました。ミルは「定常経済は必要なだけではなく、望ましい」とすら考えていました。今のアメリカでは、経済学を学んでも、こういった古典派経済学者の考え方を学ぶ機会はありません。ですから、定常経済という考え方に出合わないのです。しかし、私のころはそういった教育がありましたから、古典派経済学者たちの考え方に触れることができました。
2つめは、さまざまな環境面での代償について知ったことです。60年代、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』などを読み、大きな影響を受けました。
3つめは、ニコラス·ジョージェスク・レーゲンの「熱力学の第二法則、つまりエントロピーの法則が、経済の中で何が可能かを決定する。経済の中で増加するエントロピーは、経済が達成・維持できる規模を制約することになる」という考え方に出合い、大きな影響を受けたことです。
そしてもう1つは、1967年からの2年間、ブラジルで経済学を教えたことです。そこで、干ばつや水不足、すさまじい人口爆発を目の当たりにしました。
こういったさまざまなことから、私は定常経済に関心を持つようになりました。地球は有限であり、われわれ人間はその下位システムなのですから、いつかは成長をやめるべきだと考えるようになったのです。進歩とは、量的な増加ではなく質的な向上である、つまり成長(growth)から発展(development)へと、考えが変わっていきました。
―それはいつごろのことでしたか?
1965年から67年ぐらいです。1972年には、メドウズたちが『成長の限界』を出しました。この本が出る前から、彼らとやりとりをしており、結論は同じだということがわかっていました。
―定常経済という考え方への反応はどうでしたか?
当時、私はルイジアナ州立大学で経済学を教えていましたが、同僚たちは「変なことを言いだした」と思ったようです。世界のあらゆる問題に対する解決策は経済成長だとみんなが信じていましたから。
この大学には21年間勤めましたが、最後のほうには、学部の方向性が新古典派経済学へと向かっていきましたから、私にとってはとてもやりにくい状況になりました。
ちょうどそのころ、世界銀行が環境部門を立ち上げました。ロバート・グッドランドという、つい最近亡くなりましたが、素晴らしい人がその部門にやってきて、世銀でセミナーを行うように私を招いてくれ、その後、世銀のエコノミストとしての就職面談を受けることになりました。そして、信じられないでしょうけど、採用されたのです。
あとで聞くと、経済学者を雇いたい、しかも生態学・環境のことがわかった人がいい、ラテンアメリカに詳しい人がいい、というこの3つの条件に私が合っていたというわけです。
1988年から94年までの6年間、世銀で働きました。主に持続可能な開発の政策づくりに関わりました。
■根強い成長神話
―それにしても、定常経済を提唱しているあなたを世銀が雇い入れたということは面白いですね。
ええ、みんなびっくりしました。ロバートのおかげですね。最初の1年は試用期間で、1年後にレビューがあります。その時、私がその職にとどまることを望んでいない人も多かったのですが、ロバートがうまく働きかけて、残れるようにしてくれたのです。
もっとも、世銀には優れた人たちがたくさんいました。本当に苛立ちを感じるのは、組織にはあれだけたくさんの素晴らしい人たちがいても、その人たちが合わさると、その良さが全部打ちけされてしまうということです。リーダーシップがあるべき姿とは違うものだったのです。
それに、言うまでもなく、世銀が最も注力していたのは経済成長ですからね。成長こそがすべての問題の解決策だ、と。
―その中で、定常経済を主唱するというのはどういう感じだったのでしょう?
戦いでしたね。世銀という「身体」に、私という「ウイルス」が入ったようなものでしたから。ありとあらゆる白血球がやってきて、ウイルスを取り除こうと攻撃してきました。
しかし、助力もあったのです。私だけが定常経済を考えていたわけではなく、世銀の中にも共感する人たちがいましたし、世銀の経済学者にもこれまでの考えに疑いを持つようになっていた人たちもいます。学問の世界の経済学者に比べ、世銀に勤めている経済学者のほうが、実際の世界に出ていって何かをやろうとし、失敗する、という経験をしていますから、それだけ謙虚なのです。学問の世界の経済学者は、失敗することはありません。理論は常にうまくいきますから。ですから、現実社会からのフィードバックがかからないのです。
このように世銀にも良い面があったのですが、6年間に勤めている間に、この場所は変わることはないなと思うようになり、学究生活に戻りたいと思うようになりました。
ちょうどメリーランド大学から声がかかり、移りました。15年間、教鞭を取りましたが、経済学部ではなく、公共政策学部です。経済学者たちは、私に触れようとはしませんでした。今でも私は経済学の主流からは外れたところにいます。主流派は成長が大事だと考えている人たちですから。
―「定常経済」という考え方に対する人々の反応には変化がありましたか?
少しずつゆっくりと、関心は出てきていると思います。しかし同時に、経済成長へのコミットメントもますます大きくなってきていますよね。米国の政治を見れば、すべてが成長です。今なお、成長こそがあらゆる問題の解決策なのです。その点では、事態は改善していません。
他方、成長にはコストがある。つまり代償が伴うという認識は広がってきています。枯渇、汚染、社会的なストレスといった代償をしっかり見よう、測ろうという動きはあります。しかしまだ、そういったコストや代償を、経済成長がもたらすプラス面と分けて比べることはしていません。それができれば、「成長のコストのほうが、成長のもたらすプラスよりも大きくなっている」ということが言えるのですが。
ということで、問題について考えようという流れにはなっていますが、まだまだ成長へのコミットメントが強いというのが現状です。
定常経済への反論の1つとして出てくるのが、「1929年を見よ。当時、GDPはゼロ成長で、大不況が起こり、人々は苦しんだ。それがいいと言うのか」というものです。
しかし、この議論は「定常経済」と「うまくいっていない成長経済」を混同しています。成長を前提とした経済が成長できなければ、確かに悲惨でしょう。しかし私が言っているのは、成長ではなく、定常を前提とした経済に設計し直すということです。定常を前提として設計された経済なら、成長しなくても悲惨なものにはなりません。
―かつては経済学者も定常経済を考えていたのに、今はそうではない。どうしてそうなったのでしょうか。
2つ考えられることがあります。まず、古典派経済学は「客観的価値論」を採っていました。価値は労働や土地によって決まるという考え方です。その後、1870年代に「限界革命」が起こり、新古典派経済学が出てきました。その考え方は主観的価値論で、価値とは、労働や土地といった具体的なものではなく、効用や満足をどう感じるかによって決まる、と考えます。そこから、価格や価値の限界効用が重視されるようになり、以来、この考え方が主流となって、資源や土地などは背景に押しやられてしまいました。
資源や土地、労働といった物理的なものなら、その限界は見えやすいのですが、効用や満足といった心理的なものになると、限界は見えなくなります。どこまでも幸せになるということがあり得るかもしれない。そうではないと証明することはできませんからね。これが変化の要因の一つです。
もう1つは、その後に出てきたケインズです。大不況が起こり、ケインズ経済学が構築されました。当時の課題は失業でした。失業問題を解決するためには、投資をし、成長することが必要という考え方が重視されました。
時代柄、ケインズの関心事は短期的なことでした。短期的な問題は失業であり、失業者を雇用に戻すにはどうしたらよいか、それには成長だと考え、長期的なことは何とかなるだろうという考え方だったのです。
しかし、ケインズが何とかなると考えていたその「長期的なこと」、つまり経済成長を続けることのマイナスの影響は、数百年後ではなく、もうすでに現れ始めているのです。
興味深いことに、短期的な失業問題に焦点を絞っていたケインズも、長期的なことを考えることがありました。『孫の世代の経済的可能性』という有名な評論では、ほぼ定常経済に近いものを構想しています。ですから彼も、問題や難しさはわかっていた。ただ時代の要請により、失業という短期的な問題に焦点を当てていたのです。
その点でもう1つ興味深いのは、米国で1946年に完全雇用法が施行されたことです。完全雇用こそ国の大きな目標であると考えられていたのです。その目標に達する手段として成長が必要だ、と考えられました。
ところが、今ではこれが逆転してしまっています。完全雇用が目的で、成長はその手段であったはずなのに、今では成長が目的化している。成長のために雇用を損なうことがあったとしても、それは仕方のない代償なのだ、と。オートメーション化を進め、海外へ雇用を移転して失業が増えたとしても、「成長のためにしょうがない」と考えられているのです。
―なぜ、そうなってしまったのでしょう。
成長は、それを導いている人たちにプラスをもたらすからです。大企業など、成長やグローバル化などからメリットを得ていますから。そして経済学者は今でも、成長が貧困などへの問題の解決策だと信じています。成長すればトリクルダウンが起こって、貧しい人も豊かになるだろう、と。実際には、豊かな人がさらに豊かになっているのですが。
―でも、失業などで傷ついているはずの一般の人でも、成長こそが解決策だと信じていますよね。
そうです。アメリカでも同じです。それはなぜか、わかります。成長経済の成長を止めようとしたら、つまり成長経済が失敗したら、失業は発生するし、大変なことになります。
定常経済では、「貧富の格差の幅を制限する」という考えがあります。成長が"不経済"になり、成長がわれわれを豊かではなく貧しくする状況では、成長によって貧困を解決することはできません。そのときの解決策は再配分です。
まったく平等にすると言っているわけではありません。それは恐らく公平ではないでしょう。しかし、不平等の幅が無制限であるのも、さらに不公平だと思うのです。ですから、不平等の幅をある一定の範囲内に抑えるということです。
企業の上位と下位の給与の幅を見ると、日本企業は10~15対1に対して、米国企業では500対1もの格差があります。この点、米国は日本から学ぶべきです。
不平等の格差を制限するというと、共産主義者だ、社会主義者だと言われますが、そうではありません。格差の幅をせめて100対1にすればよい。それでも十分、仕事に対するインセンティブは出るでしょう。
(その2へつづくー)