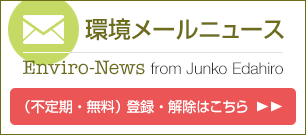エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
戦国時代の治水術(2016年2月22日掲載)
気候変動の影響の顕在化か、世界各地で大雨や洪水が増えているようです。日本でも、以前には考えられなかったほど、短時間に大量の雨が降るようになり、河川の氾濫や洪水、土砂崩れなどの被害が出ています。
多雨地帯であるモンスーンアジアに位置する日本には世界平均の約2倍もの雨が梅雨期と台風期に集中的に降ります。このような状況から、日本では昔から治水が非常に重要でした。甲斐の国での「信玄堤」が400年以上たった現在でも治水機能を果たし続けていると聞き、先日取材に行ってきました。
信玄堤はさまざまな要素から構成されていますが、なかでも面白かったのが「霞堤」と呼ばれる堤防です。
通常の河川の堤防はずっと連続して続いています。切れている所があれば、そこから水が流れ出してしまう恐れがありますから、切れ目なく堤防を作るのが「当然」です。
ところが、霞堤は所々で切れているのです。切れた後ろにもう一つの堤防があります。大雨で川が氾濫すると、堤防の切れ間から水があふれ出します。こうすることで、洪水のエネルギーを分散できるそうです。あふれた水は後ろにある堤防で受け、徐々に本流に戻す仕組みです。
決壊することを前提に作られた多重の堤防を見ながら、「堤防とは決壊しないもの」という現在の考え方は一つの思い込みなのかも知れない、と思いました。
がっちりと切れ目なく築いた堤防は強固な対策に見えますが、東日本大震災でもそうだったように、いったん決壊すると、あっという間にすさまじい氾濫と洪水が起きてしまいます。「決壊しない」ことを前提としていますから、堤防そばまで人家や商工業施設が建ち並び、いざというときの被害は大きくなります。
対照的に、一見もろそうに見える霞堤のほうが、いざというときの被害が少なくて済みます。洪水を完璧に封じ込めることを目指すのではなく、洪水が起こることを前提に、流域全体を使って水の流れを制御し、人々にも「決壊しない」と思い込ませないこの仕組みは、しなやかな強さ(=レジリエンス)の好例だと思います。「堤防をどこまで高くすればいいか」という議論も不要ですし、建設費用も少なくて済みます。
途上国でも温暖化の影響に対する防災が必須であるこの時代、「かつての技術や考え方に学び、採り入れていくことが大事だ!」と、山梨の冷たい風の中で思いました。