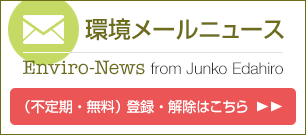エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
ブルーカーボン5つの鍵 (2025年4月21日掲載)
海藻・海草の藻場を再生することで、海の豊かさを取り戻すとともに、CO2吸収量を増やし、気候変動対策にもなる「ブルーカーボン」。日本でも世界でも大きな注目を集めています。日本のブルーカーボンの取り組みをつないで加速したいと考え、2021年にNPO法人ブルーカーボン・ネットワークを立ち上げました。私の本拠地の熱海でも、4年前から試行錯誤しながら取り組みを進めています。これまでの経験から、ブルーカーボンの取り組みをスタート・進展させていくために、5つの大きなポイントがあると感じています。
1つ目は藻場の再生技術です。減少・消滅した海草や海藻をどうやって復活・回復させればよいのか。その方法は場所や藻場の種類によって異なります。まだ「これが成功の方程式」と言えるものはなく、各地で試行錯誤が続いています。
2つ目は調査・計測技術です。海の中の藻場の現状や変化を知る必要があるからです。潜水士による調査は精度は高いものの時間とお金がかかります。熱海では水中カメラや水中ドローンを使った簡便で廉価な計測方法を開発中ですが、調査・計測は各地の悩みのタネです。
3つ目は許認可です。海の中での活動なので、漁業者はもちろん、地元の自治体や都道府県の土木事務所、海上保安庁のほか、多くの関連する人々の同意や許可が求められます。
4つ目はどうやって地元のさまざまなステークホルダーに関わってもらうか。行政だけ、漁業者だけ、NGOなど民間団体だけでは、なかなか活動が広がらず、持続が難しくなります。熱海では市役所や地元の漁業者などと連携しながら、「山と海はつながっている」と、山を守る活動をしている方々やホテルや旅館の方々など、幅広いステークホルダーに関わってもらえるプラットフォームを意識しながら活動しています。
5つ目はお金。どうやって活動を経済的にも持続可能にしていくかを考える必要があります。国の温暖化対策として、省エネや再エネ、林業への支援はいろいろありますが、ブルーカーボンへの支援は今のところほとんどないのです。
ブルーカーボンへの関心と評価が高まり、現在は多くが持ち出しで頑張っている各地の取り組みが持続可能になり広がっていくことを切に願っています。