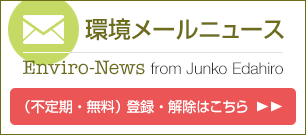エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
「2050年エネルギー情勢懇談会」に参加して(前編)
はじめに
「なんで『原発はないほうがいい』意見のあなたが、原発推進の自民党政府のエネルギー委員会に入ったの???」
昨年夏に多くの人に聞かれた質問だ。というより、そもそも、自分自身が驚いていた。「なぜ私が? 民主党政権時代、基本問題委員会で脱原発を主張し、自民党政権になったら、エネルギーはおろか、環境省などその他の政府委員会の委員も解かれたというのに?」
その委員会は、現在のエネルギー基本計画が考えている2030年を超えて、2050年の日本のエネルギー政策を考える委員会だという。しかも、政府の委員会には20人を超えるほど多くの委員がいるのが常なのに、今回の委員会は8人という少人数の委員で、しっかり議論していくのだという。
このエネルギー情勢懇談会は、8月30日に第1回が開催されてから、2月末までに7回の会合が重ねられている。ふだんは淡々としている私が思わず語気を強めた「ゲストのびっくり発言」もあれば、自分自身、深く考えさせられる場面も数多くあった。エネルギー情勢懇談会、略して「情勢懇」は現在、年度末のとりまとめに向けて、まさに佳境に入ったところである。
本稿では、日本のエネルギー政策の基本的な仕組みから、今回の情勢懇の位置づけ、7回の会合の具体的な内容と現在位置、私自身の考えなどについて、お伝えしたい。
日本のエネルギー政策のこれまで
まずは簡単に日本のエネルギー政策についておさらいしておこう。
戦後の混乱、2度の石油危機などを経て、生活水準の向上に伴う需要の増大、1997年の京都議定書締結を受けての温暖化対策という側面の浮上など、エネルギーをめぐる多様な状況に対応すべく、2002年6月、「エネルギー政策基本法」が制定された。
エネルギー政策基本法の基本方針は、エネルギーに関する「安定供給の確保」「環境への適合」「市場原理の活用」である。同法に基づき、2003年10月には、エネルギーの需給に関する基本的な計画として「エネルギー基本計画」が決定された。
エネルギー基本計画(ギョーカイ用語では「エネ基」と呼ぶ)は、少なくとも3年ごとに改定されることが法律に定められているため、2007年3月に第一次改定が、2010年6月に第二次改定が行われている。
2010年版のエネ基には、以下のように書かれている。「電源構成に占めるゼロエミッション電源(原子力+再生可能エネルギー)を、現状の34%から70%へ引き上げる」ため、「2020 年までに、9基の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約 85%を目指す(現状:54 基稼働、設備利用率:(2008 年度)約 60%、(1998 年度)約 84%)。さらに、2030 年までに、少なくとも 14 基以上の原子力発電所の新増設を行うとともに、設備利用率約 90%を目指していく」。
その後、2011年3月に東日本大震災、東電福島原発事故が起こった。本来なら次のエネルギー基本計画の改定は2年後のはずだったが、菅前首相が「白紙からの見直し」を指示、2011年夏をめどに作り直しに取りかかった。ここで設定されたのが、閣僚を構成員とする「エネルギー・環境会議」である。この会議体の下に、3つの委員会が役割を分担する形で置かれた。
- 原子力委員会:原子力政策の選択肢を出す
- 総合エネルギー調査会の中に設置された「基本問題委員会」:エネルギーミックスの選択肢を出す
- 中央環境審議会:温暖化対策の選択肢を出す
私は基本問題委員会の委員の1人となった。当初の委員の顔ぶれがあまりにも原発推進派に偏っていたため、人選への批判が起こり、少しでもバランスをとるべく急きょ委員を増やしてのスタートであった。それでも総勢25人の委員のうち、原発反対の意見の持ち主は8人程度だったと思う。
「コストの安い電力の確保のために原発は不可欠」とする主に産業界を代表する委員と、原発事故のみならず、核廃棄物の処理法も場所も確定していない原発を推進するのは未来世代への責任を果たせない、再エネを最大限推進し、原発は段階的であっても撤廃すべき」とする私などとの間には大きな溝があり、対立構造のまま、原発の依存度をめぐる「国民的議論」のプロセスに入った。
全国11箇所で意見聴取会が開催され、初めての試みとして「討論型世論調査」が行われた。パブリックコメントに寄せられた意見はパブコメとしては驚異的な数である約8万9千件。そのうち、87%が「原発依存度0%」を選んでいた。
民主党の野田内閣は、公聴会やマスメディアの世論調査なども参考にして、国民の過半数が原発に依存しない社会を望んでいると判断し、「2030年代に原発稼働ゼロ」の方針を決定し、民意を政策に反映させようとした。具体的には、①40年運転制限制を厳格に適用する、②原子力規制委員会の安全確認を得たもののみ、再稼働とする、③原発の新設・増設は行わない そして、「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、あらゆる政策資源を投入する」とした。
しかし、その後、自公連立の安倍内閣に変わる。経産省は2013年12月、原発を「重要なベースロード電源」と位置づけた基本計画の原案を示し、それから1カ月間、パブリックコメントに付した。経産省は2014年2月、「集まった意見は約1万9千件だった」と発表し、寄せられた主な意見も明らかにしたが、「原発の賛否割合」という重要な情報は出さず、当時の茂木経産相は「数ではなく内容に注目して整理を行った」と国会で説明した。
ちなみに、「政府が公表しないなら」と、朝日新聞の記者がパブコメに寄せられた意見のすべての開示請求をし、20,929ページのコピーを20万円余りの費用をかけて入手、独自に調査して、「脱原発の意見が94%だった」と発表している。
こうして、2014年4月に「原発は重要なベースロード電源」と位置づけるエネルギー基本計画が策定され、現在に至っている。
現在置かれているエネルギーに関する2つの委員会
前述したように、「エネルギー基本計画は3年ごとの見直し」が法律で決められている。現行のエネルギー基本計画は、2014年に策定されたものなので、2017年に、見直しが始まった。この見直しのために設置されたのが、「総合エネルギー調査会 基本政策分科会」である。委員数は、18名。8月9日に議論が開始された。基本政策分科会は、エネルギー基本計画の実現を重視し、課題を抽出しながら議論をしていく位置づけである。この春から夏にかけて、とりまとめ作業が終わる予定だ。
これに対して、もう少し遠い将来に向けての勉強と議論を始めるために設置されたのが、私が参加している「エネルギー情勢懇談会」である。「2050年視点での長期的なエネルギー政策の方向性を検討する」ため、経済産業大臣主催の勉強会として新たに設置されたものだ。
資源エネルギー庁のウェブサイトには、次のように位置づけが述べられている。
我が国は、パリ協定を踏まえ「地球温暖化対策計画」において、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの下、主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指すこととしています。
他方、この野心的な取組は従来の取組の延長では実現が困難であり、技術の革新や国際貢献での削減などが必要となります。このため、幅広い意見を集約し、あらゆる選択肢の追求を視野に議論を行って頂くため、経済産業大臣主催の「エネルギー情勢懇談会」を新たに設置し、検討を開始します。
エネルギー情勢懇談会のメンバーは8人。五十音順で、飯島彰己氏(三井物産株式会社代表取締役会長)、 枝廣淳子(東京都市大学環境学部教授、有限会社イーズ代表取締役) 五神真氏(東京大学総長)、坂根 正弘氏(株式会社小松製作所相談役)、白石隆氏(独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所所長) 、中西宏明氏(株式会社日立製作所取締役会長)、船橋洋一氏(一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ理事長)、山崎直子氏(宇宙飛行士)である。
会合は基本的に全て公開で行われ、資料も会合の動画もすべて公開されている。
ちなみに、「なぜ私が委員の一人に選ばれたのですか?」とエネ庁関係者に聞いてみたことがある。「今回はさまざまな立場から幅広い議論をしてもらいたいので、この顔ぶれになった」「環境問題に詳しい人も必要だという判断もあった」などの答えだった。少しでもジェンダー・バランスをとりたい、という意図もあったのかもしれない。
かくして、8月の第1回を皮切りに、2月末までに7回の会合に参加してきた(すべての資料と動画は資源エネ庁の情勢懇のウェブサイトから入手・視聴可能)。
エネルギー政策に対するパリ協定の影響
今回のエネルギー情勢懇談会が設置された最大の理由は、パリ協定を遵守するためのエネルギー政策を考える必要性である。「現在のエネルギー政策や、従来の議論の延長上では、パリ協定はとても到達できない」という問題意識なのだ。パリ協定に向けて、政府としての方針をしっかりと固めていくことが大きな目的の一つであると理解している。
日本の排出している温室効果ガスの9割以上が二酸化炭素であり、その大部分がエネルギー起源であることから、温暖化対策とエネルギー政策は、コインの両面である。3.11後、原発の稼働がほぼゼロとなり、再エネはまだ十分な発電容量になっていなかったため、日本の電源構成に占める天然ガスや石炭による火力発電の割合がポン!と上がった。火力発電の割合は、2009年当時は61.7%だったのが、2015年時点では、84.6%となっている。化石燃料の中では天然ガスが最大で44.0%だ。世界中の「脱石炭」の動向に逆行して、日本では石炭火力発電の割合が2012年の27.6%から2015年には31.6%へと増加している。
このような「3.11後の火力発電シフト」の当然の結果として、日本のエネルギー起源のCO2は、震災前の11.4億トンから、震災後には、12.4億トンへと増加。電力の排出係数も、2010年の0.42kgCO2/kWhから、0.52 kgCO2/kWhへと大きく悪化し、「企業や家庭ががんばって省エネしても、CO2排出量が減らないか増えてしまう」という状況を生んだ。このように、エネルギーと温暖化対策は表裏一体なのである。
そもそも、エネルギー政策基本法が策定された背景にも、京都議定書が締結されるなど、温暖化対策の重要性が大きくなってきたことがあった。以来、どのエネルギー基本計画でも、「エネルギー起源のCO2をいかに削減するか」は柱の1つとなっている。
前述の2010年版のエネルギー基本計画では、2030年までに、少なくとも14基以上の原子力の新増設、原子力設備利用率の引き上げとともに、再生可能エネルギーの最大導入によって、電源構成に占めるゼロエミッション電源(原子力+再生可能エネルギー)を70%に引き上げるとしているが、それによって、「エネルギー起源CO2は、2030年に90年比30%削減できる」としている。
経産省やエネ庁は「原発ありき」で政策をつくっているとよく批判されているが、おそらく、「原発ありき」というイデオロギーというよりも、経済や産業、暮らしへの電力供給を途絶する恐れなく、国際社会に求められているCO2削減を実行するとしたら、再エネがまだ足りていない状況下では、原発がこのくらい必要だ、という考え方なのだろうと思う。
今回のエネルギー情勢懇談会は、まさにその設置根拠が「パリ協定を踏まえ、2050年に温室効果ガス80%削減」を実現するエネルギーを考える、となっているように、パリ協定への対応として生まれた委員会だと言うこともできる。第1回から第7回までの会合も、「原発は必要か、不要か」という議論ではなく、「エネルギー供給を途絶することなく、いかにエネルギーと経済の低炭素化をはかるか」を考えるための場として位置づけられる。つまり、原子力政策についても、「あらゆる選択肢の一つ」として議論の対象となるが、あくまでも「2050年の温室効果ガス80%削減」という極めて高い目標に向けてのエネルギー政策を、様々な観点から考えていくのが情勢懇だと理解している。
第1回の会合では、事務局資料として、「パリ協定下の2050年の温室効果ガス削減について、先進国は極めて野心的な高い目標を共有」とし、各国の目標をいくつか提示した。米国とカナダは05年比80%削減、ドイツは90年比80~95%、フランスは90年比75%の削減目標を掲げている。それらと並んで、日本の「2050年に2013年比80%削減」という目標が掲載されている。
ちなみに、日本の温暖化の長期目標について、2008年、洞爺湖サミットを控えたタイミングで、当時の福田総理のもと、首相官邸に「地球温暖化問題に関する懇談会」が設置され、議論を重ねた。私はこの委員の一人だった。企業の競争力への悪影響などを心配して、できるだけ低めの目標を設定しようという経済界代表の委員と、「温暖化を止めるために、あるべき削減目標をめざすべき」とする私たち市民派の委員とのバトルを思い出す。最終的には、「日本は2050年までの長期目標として、現状から60~80%の削減を目指す」とする最終提言がまとまったのだった。その後、「2050年に80%減」という長期計画が閣議決定され、日本の長期目標として位置づけられたのだった。
情勢懇会合の私的ハイライト
これまでの情勢懇の中から、特に自分が大事だと思ったことや自分の発言を中心にお伝えしよう。すべての資料や会議の動画は公開されているので、関心のある方はそちらを参照いただきたい。
第1回(2017年8月30日)
第1回は、顔合わせと事務局からのデータや論点の提示が主な内容だった。
私は自己紹介で、「この懇談会の議論に、3つの視点をもって参加したい」と述べた。
1つめは、「環境」の視点である。「この情勢懇自体、パリ協定の野心的な目標を前提としているので、温室効果ガス排出量については十分に議論されるはずだが、その議論が世界的にどのように位置づけられるのか、世界の動向も見ながら考えていきたい」。
2つめは、「地域」の視点だ。人口減少と高齢化が進む日本では、地域のエネルギーをどのようにまかなうかが今後ますます重要になってくる。2050年になっても、今と同じように、大型の発電所から全国津々浦々の家庭まで長い送電網で送電している状況は考えられないし、あってはならない。大容量の安定した電力を必要とする工業用途は2050年にも大規模発電所に依存しているかもしれないが、多くの家庭では、屋根上の太陽光発電とその頃には安価になっているであろう充電池、または電気自動車を電池代わりに利用することで、エネルギーの自給自足を実現しているだろう。
そして、それぞれの地域が、地域内で発電した電力を地域内で融通する仕組みを持ち、送電ロスもなく、海外情勢による輸入エネルギーの途絶があっても地域の暮らしや経済が混乱することもなく、レジリエンスの高い地域になっているという絵姿を描きたい。これまでは、そのような地域のエネルギー自立をめざす技術や法的な枠組みは余り重視されてこなかったが、この情勢懇では、大きな柱の一つに位置づけてほしいと考える。
3つめは、「市民」の視点である。原発事故から6年以上たち、エネルギーに関する意識や、市民が議論する場も減っている。日本では、環境意識もエネルギーへの関心も減ってきているという世論調査も多い。望ましいエネルギーの未来を創り出すためには、専門家だけに頼るのではなく、私たち一人一人が知り、考え、議論し、発言することが何よりも大事だと思う。そのために、自分にもできることとして、情報提供のウェブサイト「エダヒロのエネルギー情勢懇談会レポ!」を立ち上げ、ここでのデータや議論を広く伝えていきたい。
各委員の自己紹介後、事務局からの資料説明。このような委員会や懇談会では、事務局が議論のたたき台として、データや論点の整理をしたものを提供することが多い。第1回の情勢懇でも、参考資料として、事務局からの「エネルギー選択の大きな流れ」が提示された。
「主な情勢変化、今後その見極めが重要」として挙げられていたのは、次の8つである。①油価と再エネ価格の下落、②蓄電池開発の本格化と現実、③脱原発を宣言した国がある一方、多くの国が原子力を活用している状況、④自由化と再エネ拡大、悪化する投資環境、⑤パリ協定、米国離脱もトレンド変わらず、⑥拡大する世界のエネルギー・電力需要、⑦新興企業の台頭、金融の存在感、⑧高まる地政学リスク、求められる戦略。
この事務局の説明に対して、私はまっさきに手を挙げてこう発言した。「長期的なエネルギー政策を考えるにあたっては、従前の『輸入メンタリティ』から脱する必要があるのではないか」。事務局の「見るべき情勢」の8つの多くは、「海外からエネルギーを安定的に輸入する」ことを使命とする"これまでのエネ庁"の視点と何ら変わらない。
2030年に向けてなら、それでもよいかもしれない。しかし、2050年を考えるのであれば、個々の家庭など小規模でも発電できる技術が普及し、地域にあるエネルギー資源を活用できる時代にふさわしい視点が必要だ。「輸入メンタリティ」から脱却して、たとえば、個人や地域のエネルギー地消地産の仕組みを支援するなども大事になってくる。
さて、最後のエネ庁長官と世耕経産大臣からのコメント後に、「最後にどうしても、という人がいますか?」という司会の方からの問いかけに、私は再び手を挙げて、こう述べた。
「このレイアウトは、おひとりさまの個別ブースの焼肉店のようで、エネ庁側は見えても、委員がお互いに見えない。委員の間でもやりとりをしたいので、机の配置を斜めにするなどして、お互いの顔が見えるようにしてほしい」。
座席は、いわゆるコの字型で、こちら側に委員が横に並び、向こう側にエネ庁側が並んでいる。横長の机に、一列に委員が並ぶので、お互いが見えないのだ。それぞれが前に並んでいる官僚に話しかける形になってしまい、これでは「懇談」はできない。「学習する組織」の考え方の1つに、「場の質が関係性の質を左右する」というものがある。「場の質→関係性の質→思考の質→行動の質→結果の質」とつながるのだ。この懇談会が本当によい議論につながり、よい結果につながるために、机の配置を変えてほしい!と発言したのだった。
「おひとりさまの個別ブースの焼肉店」というたとえには会議室に笑いがもれ、エネ庁側から「次回は工夫します」との返事を得て、第1回は散会となった。
その後の流れ
第2回に参加して、まずうれしかったのは、前回最後の発言を受けて、座席がラウンドテーブルにしつられてあったことだ。直線上に向き合う形に比べて、場の雰囲気も柔らかくなり、「懇談」しやすい感じだ。事務局が柔軟に対応してくれたことはすばらしい。
この回から第7回まで、海外のゲスト・スピーカーを招いて、2050年のエネルギーを考える上で重要な知見を得る、というプロセスが続くことになる。大きなくくりとしては、4つ設けられており、「エネルギーをめぐる地政学的リスクの動向」(第2回)「温暖化対策とエネルギー政策」(第3、6回)「エネルギー企業の経営戦略」(第4、5回)「技術とイノベーション」(第6、7回)である。
4つのくくりはエネ庁の事務局が主に考え、それぞれのテーマに対して、「答えありきでゲストを決める」のではなく、「とりまとめに両論併記できるよう、多面的な立場や意見の方々を招く」意図を持って、ゲスト・スピーカーの選定が行われていた。それぞれ非常に多忙な8人の委員のスケジュールを最大限合わせたうえで、海外から第一人者を招聘するというロジは本当に大変だったことと思う。そのおかげで、委員をはじめ、動画中継の視聴者も、あとで資料や議事録を読む関心ある人々も、15人もの第一人者の知見を共有することができた。
自分の意見がなかなか発表できず、「いつになったら議論するのか」と苛立ったこともあったが、今にして思えば、これだけ厚く広く世界の有識者や実業家の見通しや戦略を全員で共有できたのは、よい進め方だった。最初から委員の間での議論を始めていれば、それぞれの立場やこれまでのスタンスからの議論に終始し、当初の意見を持ち寄ってのとりまとめになっていた恐れがある。学びの体験を共有することで、ひとつ先に進める可能性が拓かれる。
ちなみに、世界的に注目されている「学習する組織」などの組織開発やリーダーシップ開発の手法に、「ラーニング・ジャーニー」がある。多様な背景や視点をもつメンバーで構成するグループが、「リアル」な課題に直面する当事者を訪ねてストーリーを聞き、その体験を個人やグループで内省するプロセスであり、U理論を使った個人、組織、超組織での変容プロセスにも活用されている。内省とその共有が十分できたかどうかはともかく、さまざまな有識者や企業の当事者から話を聞き続けたこのプロセスは、私たち委員にとっての「ラーニング・ジャーニー」的なものだったのかもしれない。
第2回(9月29日)
ゲスト・スピーカーは、ポール・スティーブンス氏(英国王立国際問題研究所特別上席フェロー)と、アダム・シミンスキー氏 (米国戦略国際問題研究所エネルギー地政学議長)で、事務局からは主に、化石エネルギーの価格やそれらをめぐる地政学的なリスクなどをめぐる議論に資するインプットを要請していた。
2人の発表には、discontinuity(不連続)、disruption(途絶・混乱・崩壊)、uncertainty(不確実性)ということばが繰り返し出てきた。「2050年を考えると、地政学的にも、おそらく技術的にも、現状とは不連続の状況が出現し、その過程には数々の途絶や混乱、崩壊が生じ、しかも、何がいつ起こるか、起こるか起こらないかさえ、不確実である」というのが2人の感覚のようだった。「2050年のエネルギー政策を考えようなんて、スゴイですね(そんなこと、できるんですか?)」「2050年を予測するのはimpossible(不可能)だ」といったコメントすらあったほどだ。
この回を通して、「2050年のエネルギーを考える」ことは、もっと近い将来を考えるのとはまったく異なるアプローチが必要だということが共有されたと思う。短中期的な将来であれば、現状をベースに「これがこうなるだろう」「あれがああなるかもしれない」と予測を立てて、「ではどうしたらよいだろう」と考えることができる。しかし、2050年という、30年以上先をにらんで、日本のエネルギー政策を考えるとしたら、「中東がどうなっているだろうか」「油価がどう動くだろうか」といった、現状をベースにした予測や推測に頼ることはできない。
ではどうしたらよいのか? この点については、情勢懇後の立ち話でも聞いたのだが、二人とも「大事なのはレジリエンスのあるエネルギー政策にしておくこと」と同じ返事が返ってきた。「レジリエンス」とは、外的な衝撃に対して、ぽきっと折れずに、しなやかに立ち直る力のこと。これからの不安定で不確実な時代に向けては、「どのような状況になろうとも、折れないエネルギー体制」にしておくことということだ。それが具体的にどのようなものなのか、どういう政策がそれに資するのかは、今後の議論の論点となると考える。
→(後編)につづきます