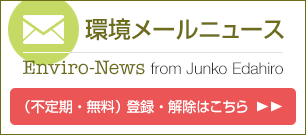エダヒロ・ライブラリー執筆・連載
「2050年エネルギー情勢懇談会」に参加して(後編)
出典:岩波書店 「世界」別冊 no.907 2018年4月号
(前編)はこちらをご覧ください
第3回(11月13日)
テーマは「地球温暖化対策とエネルギー政策について」、事務局から事前に出した質問は、「国際的な温暖化対策の長期方針」「再エネ」「原子力」「電化の進展と低炭素技術の可能性」についてだった。
ゲストは予定では3人、マイケル・シェレンバーガー氏(米国のエネルギー環境団体エンバイロメンタル・プログレス代表)、ジム・スキー氏(英国インペリアル・カレッジ・ロンドンの教授、イギリス政府に対して2050年までの長期地球温暖化対策の枠組みを提言する気候変動委員会の委員、IPCC議長)、クラウディア・ケンフェルト氏(ドイツの環境経済学者)だった。ドイツのケンフェルト氏は体調不良のため不参加となったこともあり、人選も内容も、原発推進に偏った、バランスを欠いたものになってしまった。
私はふだんはあまり激高しないタイプだが、シェレンバーガー氏の発言はさすがに腹に据えかねて、その思いを口にした(が、のれんに腕押しだった......)。
シェレンバーガー氏は、「温暖化への解決策は原発しかない!」というスタンスで、「パンドラの約束」という映画でも話題になった環境活動家だ。「石炭火力による大気汚染では700万人が死んでいるが、原発事故で死んだ人はほとんどいない。原発は最も信頼性があり、安全な発電手段であるから推進すべきである」という考えの持ち主である。
氏の発言を抜粋引用する。「チェルノブイリや福島に関する事実を見せると、『チェルノブイリ原発事故で亡くなったのは200人に達していない』ということに驚く人が多い。同じように、福島原発事故に関しても、ほとんどの死亡はパニックや避難によるものだ。チェルノブイリの追加的な放射線のリスクは驚くような数字で、大都市に住んでいる人のほうが死亡率が高い。一方、化石燃料やまたバイオマスを燃焼することによる大気汚染で、毎年700万人が死亡している。こういった結果を見ると、原子力が最も信頼性があり、電気を生み出す安全な手段であるということがわかる」。
福島の状況を語った際のパワーポイント資料には、以下の内容が掲載されている。
- 放射線による死者はなし
- パニックや避難、ストレスから1500人以上が死亡
- 津波によって15,000人以上が死亡
- 甲状腺がんの増加は全く見込まれない模様
- 有害な妊娠影響もなし
また、石炭・石油・バイオマス・天然ガス・原子力の「1TWhあたりの事故による死者数」「大気汚染による死者数」を比べるグラフを載せて、「原子力は既に、信頼性ある電気を生み出す最も安全な手段である」と結論づけた。結びの言葉は、「最後に伝えたいのは、原子力のみが、私たちが気にかけている目標を達成することができるということだ。原発だけが環境保護に貢献しつつ、世界平和をもたらしながら全人類を貧困から脱却させることができる」。
質疑応答になって、まず私が発言した。「最初が、原子力発電のリスクに関してだが、大きく『事故のリスク』と、『核廃棄物の処理の方法や場所が決まっていない』という2つのリスクがある。事故に関しては、先ほど、『事故は起こるものだ。しかし、福島で、それで直接的に亡くなった人はいない』といろいろデータを示して話されたが、その発言は、多くの日本の人、特に福島の人々の神経を逆なでする話だったということを一人の日本人として伝えたい。その上で、話になかった核廃棄物の処理についてどう考えているかを聞きたい」。
氏の回答には、福島の原発事故の被害者や被災者に対する共感はみじんも示されず、私の質問への答えもなかった。
2人目のゲスト・スピーカーのジム・スキー氏は、「シュレンバーガーさんとはちょっと違うお話をしたい」と前置きして、英国の温暖化・エネルギーへの取り組み、その効果および課題もわかりやすく伝えてくれた。かなり強烈な原発推進者がトップバッターだっただけに、バランスをとることを期待していたドイツのゲストが参加できなかったことが返す返すも残念だった。
第4回(12月8日)
第4回は、「エネルギー事業者の経営戦略」をテーマに、原子力事業を中心に展開する米国エクセロン・コーポレーション社、石油・ガス事業から撤退して洋上風力発電を中心に再エネ事業を展開するデンマークのオーステッド社の話を聞きた。
エクセロン社からは、「原子力安全文化」をどのようにつくり、維持しているかを聴き、一人ひとりが安全への思いと訓練を保ち続けるしくみを持つことが、原発神話に思考停止せずにすむ道だったのだろうと思った。その前提は、「事故は起こりうる。そして防ぎうる」という信念なのだ。
オーステッド社のゲスト・スピーカーは、日本にも洋上風力発電のポテンシャルは大きいこと、実際にそれを開発していくためには、規制をしっかり明確にすること、日本がどこまでをめざしているかを明確にすることが必須であることを強調していた。台湾で洋上風力発電の開発を進めているとのこと、日本でもぜひ!と願う。
第5回(2018年1月31日)
テーマは、「世界の総合エネルギー企業にその経営戦略を聞く」というもので、世界的な石油メジャーのロイヤル・ダッチ・シェルの上級副社長(ウェブ参加)、世界最大の原子力事業者であるフランスのEDFグループの上級副社長、ガスを中心とした火力発電を軸に、水素事業なども展開するENGIE社の上級副社長のプレゼンを聞き、質疑応答を行った。
この回の、特にシェルのプレゼンならびに質疑応答は、情勢懇の議論にとって、大変重要なインプットとなり、「日本の常識は世界の非常識? 化石燃料会社が炭素価格づけを熱望!」という見出しをつけて、ウェブのレポ!にも報告した。
日本では、炭素税や排出量取引など、炭素に価格をつけることで排出量を削減しようという動きに対して、「そんなことをしたら企業のコストアップになって経済の足をひっぱる」という反対が強く、試行的・限定的にしか行われていない。炭素に価格がついたとき、最大の影響を受けるのは化石燃料会社であろう。だから、シェルは「炭素価格には絶対反対!」だろうと思っていた。
ところが! シェルでは、何年も前から政府に「炭素価格を導入するよう」要請しているとのこと。世界銀行の「カーボン・プライシング・リーダーシップ・コアリション」にも参加し、全世界で炭素価格が導入されるよう協力しているのだ。
「どうして?」という私の質問に対する答えは、「製品コストの中に炭素価格を入れることで、シェルのような企業も含めて合理的な経済判断ができるようになるからです」。政府に要請するだけではない。シェルではすでに1トン40ドルという社内炭素価格を設け、主要な投資案件の判断に用いているのだ。それは、「カーボン・プライシングが導入されたときに備えて、十分な対応能力を確保しておく」ためでもある、との説明がなされた。
第6回(2月19日)
この回は、体調不良で欠席となってドイツの知見を得ることができなかった第3回のフォローアップとして、フェリックス・マッティス氏(ドイツエコ研究所、欧州委エネルギー総局委員)をゲスト・スピーカーに、「地球温暖化対策とエネルギー政策」についてのプレゼンを聞き、質疑応答を行った。欧州委員会のエネルギー総局に所属し、2050年までの欧州全体のエネルギーロードマップの策定にも関わっている方で、ドイツのみならず欧州全般を視野にお話をいただいた。
そのあと、「技術・イノベーション」の1回目として、リチャード・ボルト氏(オーストラリア・ビクトリア州 経済開発・雇用・運輸・資源省次官)と、今回唯一の国内からのゲスト・スピーカーの内山田竹志氏(トヨタ自動車 代表取締役会長)のプレゼンを聞き、質疑応答を行った。
マッティス氏のセッションで、日本の2050年に向けてのエネルギー政策が参考にすべきと思った点が3つある。
1点目は、私自身の最大の関心事でもあるが、地域のエネルギー事業としてよく知られているドイツの「シュタットベルケ」である。シュタットベルケは、ドイツ各地で、電力事業(発電・配電・小売)やガス供給といった地域エネルギー事業と、水道、交通などの生活インフラの整備・運営を担う小規模の地域密着型事業体である。現在ドイツ全体で約900社存在し、ドイツの電力小売市場の約20%のシェアを有するという。
マッティス氏は、「市町村を基盤とする電力会社が急増している」という。シュタットベルケは配電網も所有しているので、電力の融通性の重要な担い手になっているのだ。「ドイツで再エネがこれほどうまく展開した理由を述べると、その4割はFIT(固定価格買取制度)のおかげだが、ちょっとやりすぎてお金がかかりすぎた感じがあるが、払う価値はあった。成功理由の3割は、アンバンドリング。各投資家がグリッドのアクセスをきちんと認められたので、競争条件が平等になり、新しい投資家が参入するようになった。残りの3割は、シュタットベルケなど市町村や協同組合が発電をやっていたことだ」。
日本でも、"ご当地電力会社"など地域型の電力・エネルギー事業も増えてきているが、2050年には地域や家庭用のエネルギーはこうした地消地産型でまかなうような絵姿を描き、そのための制度設計や技術開発を進める必要がある。
2点目は、「再エネの割合が30%を超えてくると、"ベースロード"の果たす役割が小さくなってくる。50~55%を超えると、"ベースロード"という概念自体が消える」という発言だ。
日本では、現行のエネルギー基本計画も含め、「ベースロード電源としての原発の重要性」が語られることが多い。「再エネは変動するから、ベースロード電源とはなりえない」ということだが、再エネが十分に入ってきて、需要や発電量の予測の精度が高まり、瞬時に需給ギャップを調整できる技術が入ってくれば、「ベースロード」という概念そのものがなくなるのだ。そういった状況を想定して、技術開発や制度設計を進めるべきだろう。
3点目は、欧州では、火力発電所などから分離・回収したCO2を地中に貯留する CCS(二酸化炭素回収・貯留)プロジェクトのほとんどが止まっている、ということだ。3つの理由があるという。1つは、再エネが大きく伸びているので、CCSの必要性が減っているということ。第2の理由は、社会的受容性。CO2をどこの地下に貯留するのかについて、ほとんどのEU諸国では社会の合意がとれていない。最後に、CO2をどうやって輸送するのか。そのための新しいインフラが必要になる。イギリスでプロジェクトの計画があったが、候補地となった地域の賛成が得られなかった。EUでは現段階ではCCSについては進展していない。
日本でも、「CO2削減の奥の手」「火力発電を続けるための条件」として、CCSへの期待の声を聞くことも多く、苫小牧では大規模実証試験実験が行われている。しかし、私は、核廃棄物と同じく、地震国・日本で、大量のCO2を地下に貯留することの可能性と現実性がどれほどあるのかわからない状況で、「あとでCCSをつけるから」と火力発電を進めてはならないと考えていたので、欧州の現状は参考になった。
第7回(2月27日)
前半は、「技術・イノベーション」の第2回として、NuScale社から開発を進めている小型モジュール原子炉について、マジュマダール・スタンフォード大学教授から次世代電力システムについてプレゼンを聞き、質疑応答を行った。
「cost of energy ではなく、cost of synergyが重要だ」というマジュマダール教授の指摘が興味深かった。「再エネがこれほど安くなるとは、10年前にはだれも予想していなかった。問題はもはや発電コストではなく、融通性のある形でエネルギーを統合していくコストである」。そのために必要なことは、送電網や、揚水発電やガス火力などの調整電源、安価な再エネに生産する水素・メタンなどの新技術に加えて、多地点で発電される変動再エネ電力を、分散コンピューティング、ネットワーク、AIや機械学習によって、人間の判断を介することなく変動する需要にマッチングしていくデジタル自動化システムであるとして、bits and wattsという次世代電力システムの開発を行っているという。
後半は、ファティ・ビロルIEA(国際エネルギー機関)事務局長より、2050年に向けたエネルギーの総括的なプレゼンを聞き、とりまとめに向けての問題提起として、私から9つのポイントを共有した(後述)。
ゲスト・スピーカーの布陣
このように、第2回から第7回まで、合計15人のゲスト・スピーカーを招聘して、それぞれの知見や主張を聞くことができた。その内訳をみると、エネルギー地政学の学者(2人)、原発推進活動家(1人)、温暖化とエネルギーの専門家(2人)、電力システムの学者(1人)、エネルギー全般の専門家(1人)、のほか、実際の事業に関わる立場からは、主力事業・発表の主眼をもとに分類すると、原子力(3人)、化石燃料(2人)、再エネ(1人)、水素(2人)となる。会合を見守る人々からは「原発推進のゲストが多いのでは」という声が聞かれたが、たしかに、原子力に関わるゲストが多めであったといえよう。
2050年のエネルギー政策を考えるにあたって
第7回の後半に10分いただいて、「とりまとめに向けての9つのポイント」を発表させてもらった。
①"未来の考え方"を変える
多くのゲスト・スピーカーから、繰り返し「不連続」「不確実」という言葉が聞かれた。これからの未来には複数の経路があるので、従来型の予測は不可能だし役に立たない。不確実性を前提とした考え方が必要だということで、従来の「決め打ち型」のエネルギー政策のつくり方を変えていかなければならない。その1つのアプローチとしてシェルから話があったシナリオ・プラニングを進めていきたい。
また、「未来は不確実なので、すべての選択肢をバランス良く」と言われるようになるだろうが、「すべて」と言っても論外なもの(あまりにもコストがかかる、あまりにも危険など)は選択肢に入らないことと、「バランス良く」というのは「等分」ではないことを確認しておきたい。
②減少する2050年のエネルギー需要をベースに考える
現行のエネルギー基本計画では、エネルギー需要が変化するという認識が薄い。2000年から2016年までの間に日本全体の最終エネルギー消費は14%減、一人当たりも16%減っている。一方、2050年には人口は4分の3に減るとの予測なので、「2050年の日本のエネルギー」は、一人当たりエネルギー消費が変わらないとしても、25%程度小さくなっていくエネルギー需要をどう満たすか、を考えるべき。従来の「増え続けるエネルギー需要をどう満たすか」とは考え方を変えていく必要がある。
③再エネを高らかに掲げる
エネ庁ではすでに「再エネを主力電源に」と言っているが、国民にはそういう位置づけになっているとは伝わっていない。これまでのエネルギー基本計画を調べると、具体的施策を説明するページにおける再エネの割合は、原発や化石燃料に比べてまだ少ない。今回は再エネをしっかりと高らかに掲げるべき。そのためには、再エネについての長期的な目標値やロードマップをつくり、再エネ普及を阻んでいる規制等に手を打っていく必要がある。世界の潮流である「再エネ100%化」をやりたいという企業は日本にも多いが、まだコストが障壁となっている。この壁を打ち破る具体的な施策が必要だ。
④地域エネルギーをいかに支えるか
日本の人口3万人以下の自治体の人口を足すと、日本全体の約8%にしかならないが、それらの自治体の面積を合計すると日本の国土の約48%になる。つまり、8%の人たちが48%の国土を守ってくれているのだ。そういった小規模な自治体の住みやすさや経済を支えていくことは国にとっても重要だ。
どの地域でも地元経済の最大の"漏れ穴"が「エネルギー」だ。わずか2,500人の村でも毎年7億円がエネルギー代金として流出しているという調査もある。私が関わっている北海道の下川町では、13億円近くがエネルギー代金として流出していた。下川町は、地元の森林資源を用いてエネルギーを自給した場合の経済効果を計算したところ、40億円近くのプラスと100人の雇用が生じることがわかった。そこで、下川町ではバイオマスボイラーを導入し、熱の自給の取り組みを進めている。現在町の熱の自給率49%、2~3億円のお金が地域にとどまるようになったと見られる。町の総CO2排出量も18%削減されている。
このような「地域のエネルギーを地域でつくっていく」、エネルギーの地消地産を支援することが重要。これまでの日本には、そういった制度や技術を支援する仕組みがなかったが、新しい方向性として強く打ち出すべきである。そうすることで、2050年には多くの家庭がオフグリッド化し、地域内でのエネルギーのやりとりができるようになると、地域の自立にもつながる。特に、FIT後に、その再エネを地域のエネルギー生産拠点にしていくための技術開発や制度設計が大事である。
これまでも「地域のエネルギーが大事」と発言してきたが、いつもスルーされている気がする。エネ庁が経産省にある限り、経済・産業のためのエネルギー以外は考えにくいのかもしれない。エネ庁を独立させるか、総務省に地域エネルギー担当部門をつくる必要があるのかもしれない。
⑤「ベースロード」後の世界への準備を(前述)
⑥電力(25%)以外のエネルギー、特に「熱」の議論を進めるべき
これまで電力の議論を中心にしてきたが、エネルギー全体の中で電力が占める割合は25%、つまり4分の1にしかすぎない。半分近くを占める輸送用エネルギーや、電化できない産業用の熱などへの対策も忘れてはならない。
⑦カーボン・プライシングを含む、エネルギーシフトのための政策ツール検討を
エネルギーシフトへのインセンティブを与える政策ツールについても、今回の取りまとめで取り上げる必要がある。シェルから「カーボン・プライシングが大事だ」という発言があったが、日本では、炭素に価格をつけることに対し、産業界からの反対が強く、炭素税も排出量取引も国レベルでは行われていない。海外の導入事例を見ると、炭素価格が高いほどCO2削減が進んでおり、炭素税を導入した国でもGDPは増え続けている。日本でも石油石炭税などは確かにあるが、道路輸送部門に偏っており、炭素税としてはカバー率が低い。
中国の排出量取引制度のパイロット事業に対応している日本企業もあり、国内でもすでに50社近くが社内炭素価格を導入している。こうした知見も集め、より良い形で炭素価格制度やその他の政策ツールを検討していく必要がある。
⑧将来の原発の位置づけをあと送りせず、考え始める
これまでは、エネルギーが足りないから、コストが安いから、と原発は「エネルギー政策」として扱われてきた。しかし、「廃炉技術や原子力の科学技術を絶やさないために必要」という声もある。
もし、原発がなくてもコスト的にも問題がない形でエネルギーが足りるようになったら(2050年を考えれば、世界的な動向からも再エネは十分にその責を果たすだろう)、「それなら原発は不要」と結論づけるのか、それとも、「それでも原子力の科学技術など別の理由のために必要」なのか? もし後者なら、数十基はなくてよいだろう。どのような原発をどのくらい何のために必要とするのか、という議論が必要である。
核廃棄物は特にだが、原発をめぐっては、社会的な合意形成が非常に大変で、おそらく20年か30年か、もっとかかるかもしれない。しかし、そういう話し合いをどこかで始めないことには進まない。どういった形で社会的な合意形成のプロセスを組み立てていくか、本気で考えていく必要がある。
⑨「エネルギー政策への国民の参画」、必要性の認識から実行へ!
エネルギー政策に国民が参画して、「ワガコト化」として考えていく必要がある。これまでのエネルギー基本計画でも「広く意見を聴取する」「参画」「双方向」「国民とともに創る」などが謳われている。特に、3.11後のエネルギー基本計画では、「コミュニケーションの必要性」が強調されているが、実行に移されていない。重要性はすでに認識されているので、どう本当に実行していくかを、今回の取りまとめにきちんと入れ、担当部署もしくは担当者を設置すべきである。
情報発信も、これまでは「政府の考えを伝えるため」という位置づけだったが、今では再エネ事業者が事業の採算性を考えるために必要な情報をきちんと出していくことが必要。日本はまだこの点でも不十分であり、再エネ普及の足をひっぱる一因となっている。
最後に
各国の2050年に向けての長期エネルギー戦略を見ると、米国は再エネ比率を55~65%に、カナダは50~80%に、ドイツは80%に引き上げることをめざしている。パリ協定は、京都議定書のように目標値が不変ではなく、目標値自体もどんどん厳しくなる仕組みだ。日本も、厳しくなり続ける目標を満たせるエネルギーのあり方を大胆に考え、大きな変化を進めていく必要がある。
これまでの議論を通じて、再エネシフトを進めるためには、ネットワークなどのインフラや、デジタル自動化技術が鍵を握ることがわかった。こういった分野での日本の技術革新は日本のみならず、世界の役に立つ。技術開発を支えていく必要がある。
情勢懇は、今年度末のとりまとめに向けて、3月にも議論を重ねる予定である。紹介してきたように、これまではゲスト・スピーカーの知見や戦略を共有する時間が主であったので、委員間での議論はこれからである。その議論をしっかり踏まえての、事務局からのとりまとめ案を強く求める。これまでよくあったように、「結論や落としどころは先に決まっており、委員会は『政府が勝手につくったのではない』という証拠づくりのために開催された」ということになってはならない。そして、そうならないよう、私たち一人ひとりが関心を持って、議論の行方と、その結果としての2050年の方向性の打ち出しを見守る必要がある。
ところで、第7回の情勢懇の翌日、新聞報道を見て私はびっくり仰天した。共同通信が「2050年にも原発重要と明記へ。報告書に原発の重要性を明記する方向で調整に入った。改定作業を進めるエネルギー基本計画にも反映させる方針」と配信し、多くの地方紙などがそのまま報道していたのだ。原発の位置づけなど、ひと言も議論していないのに!
情勢懇の事務局に確認したところ、「エネ庁では、その報道に書かれているようなことはなかったと認識しています。エネルギー情勢懇談会の議論は原則すべて公開されており、第7回についても同様です」
今後、メディアの報道も増えてくるだろう。報道されていることがすべて真実とは限らない。だれがどういう意図でどのような報道をしているのかも考えながら、複数の記事を読み比べる、実際の会議録や動画に当たってみるなど、メディアの煽る二項対立に陥って思考停止してしまわないよう、一人ひとりが注意する必要がある。
※エネルギー情勢懇談会については、以下の【エダヒロの「エネルギー情勢懇談会レポ!」】サイトでもレポートをご紹介しています